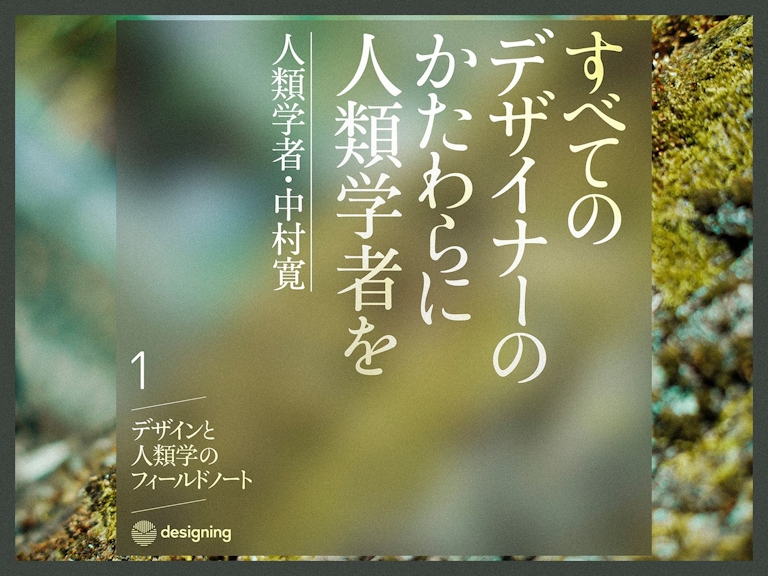
すべてのデザイナーのかたわらに人類学者を――人類学者・中村寛【連載:デザインと人類学のフィールドノート】
「デザインのための人類学」、「人類学のためのデザイン 」、そして「デザインの人類学」。これら3つに続く、第4の道に期待を寄せる。それは、デザインと人類学とが互いの領域から逸脱して、一緒になにごとかを生み出すというものである。
Design and Anthropology以前からデザインと人類学は互いの知を交換し、刺激を与え合ってきた。デザインが機会発見として人類学の手法を用いれば、人類学はデザイン実践を対象とする調査を行う。また近年では、人類学者がデザインの現場に参画する「デザイン人類学」の可能性も耳にするようになっている。
両者がともに幅広い対象を持つからこそ、多様な接点が生まれている。そう考えれば、上述したものにとどまらない、多様な実践と学びが繰り広げられているのかもしれない。
連載「デザインと人類学のフィールドノート」では、デザインと人類学が接近する領域で実践や研究に取り組む人々が、そこをどのように歩み、なにを感得したのかを探索する。「フィールドノート」と称したように、明確な結論を出すことが目的ではなく、この領域が持つ可能性を広く取り上げていく。
第1回に寄稿してもらったのは、多摩美術大学教授で文化人類学者、またデザイン人類学の実践者でもある中村寛氏。「デザイン人類学の可能性とはなにか」をテーマに、先駆的な事例やこれからの実践について前後編でお届けする。
交感してきた「デザイン」と「人類学」
近年、「デザイン人類学」と名付けられるようになった潮流が注目を集めている。とりわけ過去10年ほどのあいだに「design anthropology(デザイン人類学)」という言葉をタイトルを冠した書籍が、複数出版されていることから、そのことがわかる。
私見では、これはひとつの定まった研究領域・分野というよりは、一見するとまったくべつの要請のもと、固有の発展を遂げてきたはずの「デザイン」と「人類学」との接合のあり方を探るなかでおこなわれる数々の試みである。したがって、たとえば「経済人類学」とか「宗教人類学」「都市人類学」などと違って、一口に「デザイン人類学」といっても、さまざまな協業や切り結びの方法があり、複数の対象設定、対象へのアプローチ、触れ方がある。
もちろん、デザイン領域と人類学領域の接近は、まったく新たな事象というわけではない。過去にも、デザインが人類学の方法論や認識論との親和性に気づき、人類学(とくにそのなかでもエスノグラフィ)から学ぼうとしたことがあったし、人類学がデザインの方法から学ぼうとしたこともあった。とはいえ、すでに先行研究でも指摘されているように、それらは大別するとおよそ以下の3つの接近(ないしはかかわり)に限定されていた(*1)。
第一に、「デザインのための人類学 Anthropology for Design」。人類学のパースペクティヴ、方法、認識論や存在論をデザインに活かすというもの。たとえば、デザインリサーチやユーザーヒアリングの際に、エスノグラフィの方法論を導入するなどがこれにあたる。
第二に、「人類学のためのデザイン Design for Anthropology」。デザイン領域で培われた方法を人類学に活かそうというもの。たとえば、プロトタイピングによる試行錯誤の方法や参加型デザインの方法を、人類学に取り入れるといったものがこれに該当する。
第三に、「デザインの人類学 Anthropology of Design」。これが最も一般的な人類学のアプローチではないかと思うが、デザインやデザイナーについて、人類学的な探究をおこなうというもの。たとえば、デザイナーがどのように制作に従事するのか、デザインされたものごとが人びとの生活や認識のあり方をどのように(よくもわるくも)変化させるか、についての研究などがこれにあたる。
これら3つの接近方法も、それぞれに有意義だろうが、私としては第4の道に期待している。それは、デザインと人類学とが互いの領域から逸脱して、一緒になにごとかを生み出すというものである。
- *1:先行研究
たとえば、以下の文献を参照。Keith M. Murphy and Eitan Y. Wilf. Designs and Anthropologies: Frictions and Affinities. University of New Mexico Press, 2021; Wendy Gunn, Ton Otto and Rachel Charlotte Smith eds. Design Anthropology: Theory and Practice. London: Bloomsbury Academic, 2013.
社会からの反省を織り込み、ともにデザイン(co-design)する
デザインと人類学は、それぞれに人間と人間、人間と非人間との関係を探求し、地域やコミュニティ、社会や世界のあり方を深く見通そうとする。その点で両者は、それぞれの出発点や理論蓄積、認識の枠組みは大きく異なるものの、類似ないしは近似の探究方法をとってきたし、親和性が高いといえる。
けれども、最終的な成果物においては決定的に異なっている。一方はモノや仕組みをうみだすことで、ヒトの行動に介入し、もう一方は論文や書籍によって問いをたて、応答をつくり、議論を呼び起こす。前者が、課題を解決することで未来に(場合によっては図らずも)大きな影響を与えてしまうのに対し、後者は、課題そのものを問い直し、事象の渦中では意識的に介入を避けることで、事後的な分析にとどまる。この違いにこそ、両者のコラボレーションが実りあるものになる可能性がある。
もちろん、エスノグラフィを書くことで、人類学者は文化を書くわけで、その営みを通じて文化をデザインしていると言えなくないし、哲学者同様、論考を通じて観念のデザインにかかわっていると言えなくはない。そして、それらのアウトプットが、長い時間をかけて現実を規定していくことはあるだろうし、100〜200年後の人類の思考様式をつくっていることはありうるだろう。ルース・ベネディクトの『菊と刀』を若い大学生と読むと、「たしかに、私たち日本人は『恥の文化』だと思います!」という声が相次ぐし(もちろん、その後に批判的読解を試みる)、オスカー・ルイスの『貧困の文化』を読むことで、貧困のうちに培われる人々の文化とはこういうものだ、とその手触りをわかったかのようにふるまってしまうことができる(もちろん、それは早わかりというもので、ルイスの意図するところではない)。エミール・デュルケームの論考が浸透することで、「宗教」と「社会」とは切り離された現実の空間を構成し、やがて100年の年月を経て、ヨーロッパから遠く離れた極東の小さな島の民が、ユダヤ=キリスト教的含みをもつ「宗教」と世俗的な「社会」という概念を、日常的に使用するようになる、ということが起こる(もちろん、デュルケームだけの影響ではない)。
けれども、そうした人類学実践の現実への介入は、ごくひと握りの高名な理論家やエスノグラファーによるものだし、長い時間軸での、あるいは抽象度の高い文化の構造レベルでの話であって、一般的には、人類学の実践が現実をデザインする度合いは、商業映画やドラマ、ニューズやソーシャル・メディアとくらべて、あるいはデザイナーがおこなうデザインとくらべて、はるかにマイナーなものにとどまる。
デザインと人類学とが協業するデザイン人類学は、両者が協力し、ときにたがいを批判しあいながら、人類学の理論的蓄積、批判的精神、認識論的反省、民族誌的観察を積極的に関与させ、よりよい製品やサーヴィスを開発しようとするものである。そして、その製品なり、サーヴィスなりが生み出されたのちにも、フォローアップをおこない、よりよい方向に調整をおこなっていくこともできる。いずれにせよ、デザインのもつ未来への意図せざる介入の暴力を縮減し、産業とかけあわさったときのそのスピードに少しばかりの余白をあたえ、人間の営み、社会のあり方、世界動向などを踏まえた反省性をあらかじめ織り込んで、ともにデザインすること(co-design)――これが私が考えるデザイン人類学の姿である。
切り拓かれつつある、デザイン人類学のフィールド
このようなデザイン人類学の実践は、まったく新しい試みというわけではない。すでに応用人類学や、企業人類学、ビジネス・エスノグラフィなどの諸実践のうちにも、類似の試みがあったといえる。ひろく知られる事例はどうしても欧米圏のものが中心だが、おそらくは、同様の試みを世界各地に認めることができるはずである。
デザインファームのIDEOが、おもに人類学者がおこなってきたエスノグラフィの手法や人類学的思考を取り入れようとしていたのは有名だし、近年ではアメリカのテックカンパニーが次々に人類学者を採用している。UXリサーチのフィールドでは、もともとオーストラリアの先住民コミュニティで文化人類学のフィールドワークを重ねていたGenevieve Bell氏がインテルに採用され、今では100人以上の社会科学者やデザイナーを率いるUXリサーチャーになっているし(*2)、Rachel Fleming氏も、文化人類学者としてAmazon Web Servicesで働いていたりする(*3)。GoogleやMicrosoftなどのテックカンパニーだけでなく、メイカーやサーヴィス業者なども、デザインや研究開発などの分野で、比較的早い時期から人類学に注目してきたといえる。
- 参考文献
*2:Genevieve Bellについては、以下の記事を参照
https://www.nytimes.com/2014/02/16/technology/intels-sharp-eyed-social-scientist.html
*3 :Rachel Flemingについては、以下の記事を参照
https://americanethnologist.org/features/professionalization/so-youre-interested-in-user-experience-ux-research-thoughts-from-an-anthropologist-working-in-industry
とりわけ、コンサルティング会社などによる既存のマーケティング・リサーチなどに加え、定性的な理解の重要性に気づいた欧米圏の企業が、文化人類学をバックグラウンドに持つ人を採用するばかりか、重要なポジションにおこうとするのは理にかなっている。また、複数のスキルやバックグラウンドを持った多様性からなるチームを束ねる役割を人類学にもとめているのもうなずける。人間や非人間からなる生命圏をホーリスティックに捉えようとしてきた人類学は、そもそものスタートが学際的(multi-disciplinary)な気質をもつものだし、それゆえに、複数の専門を束ねるマネージメント的な役割を担いやすいポジションにいるのだ、と私は考える。
日本でも、日立製作所がインハウスのエスノグラファーを複数名採用していたり、最近ではソニーが文化人類学者を募集したことが話題になったりした。私自身、富士通デザインセンターのメンバーや、丸橋企画株式会社の丸橋裕史さんとともに、多企業連携のチームをつくり、エスノグラフィック・リサーチやデザイン人類学アプローチをもちいて、佐渡島の社会課題を捉えなおし、そのプロセスを振り返って抽象化するプロジェクトに参画している。そういう意味で、デザインや研究開発、経営の領域に、「静かな変革」が起きているように思える。
ただ、全体の風潮として、欧米圏と比較すると、博士号を取得し、専門的知見をもった文化人類学者を積極的に採用しようとする気運は弱い。それはおそらく、感覚や感性、雰囲気などの質的なことがらを扱い、土地や人の鼓動を感じる能力が、今後の商品やサーヴィスの研究開発にとって、そしてなによりも今後の世界における企業のあり方にとって、どれだけ大事なのかが、あまり認識されていないからということに尽きる。あるいは大事なことは頭ではわかっていても、経営陣・社員全員が腹落ちするまでには至っていないのかもしれない。定量的な理解と定性的な理解とをかけあわせるときに、あるいは定量的な理解を定性的な理解で有機的にすくいあげるときにこそ、深いインサイトが得られるのにもかかわらず。
それでも、日本において、大企業に加え、中小企業やデザインファームが、文化人類学者に注目し、彼らとともになにごとかをなそうとするようになってきているし、今後ますますそうした機会が増えていくだろう。現代社会の脳みそは数量的なものに強く反応してしまいがちだが、それだけではうまくいかないことに、感度の高い経営者はすでに気がついている。質的なことがらに溢れている人びとの生活世界をフィールドワークし、人と信頼関係を結び、彼らの叫びや言いよどみも含めた語りに耳をかたむけ、当人たちすら意識しない表情やしぐさや行動の微細な変化を観察し、言動の背後にあるものをつかみ、問いを立て、それにこたえる訓練を受けた人類学者たちが、その力を発揮できる場所は、想像以上に多い。
人類学者は、博士号を獲得する過程で、2年間のコースワークを通じて理論を身につけたのち、最低2年間のフィールドワークを経験することで、身につけた理論の前提が壊れていくという経験をする。そして、のちに戻ってきてその経験を振り返り書くことで、言葉をつくりなおすことになる。つまりは人類学の博士号取得者は、修行期間中に、自分自身の存在論的メタモルフォーゼを体験し、論文査読という苦痛をともなうプロセスを経て、最終的に博士論文を仕上げるという大きなプロジェクトを終えた者、ということになる。今後は博士号を持った人類学者が、その専門性とそれぞれの身体の固有性を持って、企業や行政などさまざまなセクターに入り、力を発揮するようになるだろうし、そうなってほしいと思う。
そのためには、アカデミアの側が、論文や報告、書籍の点数だけで業績評価するのではなく、個々の研究者がかかわったプロジェクトの質を評価できるように変わらなければならない。他の学問分野も同様かもしれないが、文化人類学の研究のアウトプットは、かならずしも論文や学会発表、書籍である必要はないはずである。地域に入ってのワークショップ、異なる分野の専門家を招いてのファシリテーション、企業の研究開発、多企業連携プロジェクトのディレクション、行政、司法、医療、看護、介護、国際政治等――いくつもの現場で人類学の知見とアイディアを「社会実装」していくことが求められているし、それこそがデザイン人類学の実践となるだろう。
スタートはかなり遅かったようだが、日本でも行政にデザインを入れようとするうごきが見られるようである(たとえば、経済産業省のJAPAN +Dなど)。だがそこに求められるのは、課題の整理・可視化と解決を志し、モデル化しやすい、単純な意味での「デザイン思考」だけではなく、哲学的洞察や認識論的反省、質的調査や参与観察を含んだ《デザイン人類学》である。
生活のなかで研究と実践を繰り返した、宮本常一というロールモデル
デザイン人類学の実践の先行例として、どのようなものがロールモデルとしてあげられるだろうか。先にあげたように、欧米圏では企業や行政セクターに入って人類学者が活躍する事例が多い。また、遊び場のようなパブリック・スペースの設計に、人類学者や社会学者がかかわる事例もあるようだ(*4)。その一方で、現実への介入という観点でデザイン人類学を構想し、とくに地域へのかかわりを考えるうえでは、民俗学者・宮本常一の身振りが参考になる。
- *4:参考文献
たとえば、Mette Gislev Kjaersgaard, “(Trans)forming Knowledge and Desing Concepts in the Desing Workshop,” in Gunn, Wendy, et al. Design Anthropology: Theory and Practice. Taylor & Francis, 2013, pp.51-67.
宮本常一は、戦前から戦中、戦後にかけて、日本全国の集落をくまなくあるき、古老たちの話をきいて記録し、メモをとるようにそれぞれの土地の景観を写真におさめ、それをもとに『忘れられた日本人』や『塩の道』『日本文化の形成』など数多くの本を著した。それと同時に、各地域での課題を調査から抽出してまとめ、離島振興法の成立に尽力したり、各地域の発展のために相談に乗ったりした。
宮本常一をデザインと結びつけて語る人はそれほど多くないだろう。ましてや、宮本をデザイン人類学者だとする人は、これまで私の知るかぎりいなかった。しかし、デザイン人類学がきりひらきつつある知の実践ーー学問(探究)と社会的介入(実装)との同時並行的・往復的実践ーーを念頭におくと、宮本の生涯の活動は、デザイン人類学のひとつとしてとらえられるようにみえる。以下、その根拠をしめしたい。
第一に宮本は、師である渋沢敬三から「君には学者になってもらいたくない。学者はたくさんいる。しかし本当の学問が育つためにはよい学問的な資料が必要だ。……(中略)……君にはその発掘者になってもらいたい」(*5)と言われ、それを忠実に実践しつづけた。このことは、宮本に徹底的に具体的なものに即してことがらを考えつづける癖をあたえたように思われる。過度の抽象化や一般化をさけ、具体的な姿・形をつうじて考えるやり方は、宮本民俗学の真骨頂だが、これは同時に、特にプロダクトなどモノをあつかうデザイナーたちがおこなっている実践にちかい。
- *5:参考文献
宮本常一『民俗学の旅』講談社学術文庫、1993、p.97
第二に、宮本は56歳のときに就職した武蔵野美術大学で、おそらくは学生からも刺激をうけ、民具や建築の研究に従事している(*6)。自伝的な著作である『民俗学の旅』でも、美術大学の学生への敬意を次のように述べている。
- *6:参考文献
この点に関しては、木村哲也『宮本常一を旅する』河出書房新社、2018.が参考になる。
美術大学に来る学生は視覚が大変発達している。したがって造形物を通して文化を理解する能力を持っている。そういう才能をのばすことこそ重要ではないかと考えて、造形文化の歴史的な変遷と、造形物と人間とのかかわりあいを中心に話をすることが多かった。すると学生たちも自分らの日常生活の中にある造形物に強い関心を示すようになっていった。生活用具・民家・集落のあり方・石造物などに深い関心を示す学生が多く、しかも興味を持つと、学校を卒業しても就職しないで、調査や研究にうちこむ者が相ついで出た。
物の本質のわかるということはすばらしいことであった。彼らは古いすすけた道具など見てもそれを汚いものとは見ないで、その中にひそむ造形的な美しさに心をひかれた。
従来の民俗学は事象の上をなぜて通るような聞き取りが多かったのであるが、美術学生は絵や図にすることが巧みで、農家や漁家にしても一軒一軒を実に丹念に測図していく。たとえば一部屋一部屋におかれている物品まで、丁寧に測図していく。それによって部屋がどのように使われているかが具体的にわかる。部屋は生きており、部屋の利用の仕方の変遷もわかる。またそのような家が組みあわさって集落ができていることもわかってくる。(宮本常一『民俗学の旅』講談社学術文庫、1993、pp.199-200.)
上のような記述をよむと、宮本が一方的に民俗学の視点を教えるだけでなく、美術のまなざしをもつ学生たちから大いに刺激をうけ、自らの培ってきた方法を練り直していったことが想像できる。
第三に、宮本は離島振興法の成立に尽力したが、いわゆる予算ありきの地域発展には懐疑的で、「離島振興法ができたから島がよくなるのではない。島をよくしようとしたときに離島振興法がいきてくるのである」(*7)と述べた。のちに鶴見和子によって「内発的発展」として概念化され論じられるような類の地域発展のあり方が、宮本によって探られていたことがわかる。これは今日、地域に携わる心あるデザイナーたちが、人類学や民俗学、社会学の視点を学びつつ、模索している道にかさなるし、同様に、心ある人類学者や民俗学者、社会学者が、従来の「観察/記述/分析」という役割から逸脱し、社会運動に参与したり、アクション・リサーチを実行したりする様子ともかさなる。このように、学問探究と人びとの生活への介入のあいだを往復するといった実践感覚をもつ研究者は宮本だけでないが、宮本の体現した姿は、これからのデザイン人類学をふかめていくうえで重要な参照軸になるはずである。
- *7:参考文献
NHKドキュメンタリー『にっぽんの地方を歩く〜民俗学者 宮本常一のまなざし〜』より。
デザイン人類学とはなにか。人類学者が社会に直接介入する実践と位置づけ、国内外の先進的な取り組みについて俯瞰的に論じていただいた。続く後編では、近年の活動を通して中村氏が見据えるデザイン人類学の実践と可能性について寄稿いただく。実践と分析や反省のバランスとは?どのような課題に、どのように取り組むのか?デザイナーと人類学者(もしくはより多くの専門家たち)の協働によって押し広げられてゆくデザインの未来を感じとっていただければ幸いだ。
中村寛(なかむら ゆたか)
人類学者。アトリエ・アンソロポロジー合同会社代表。多摩美術大学リベラルアーツセンター教授。2020〜2022年度、グッドデザイン賞外部クリティークを担当。2022年より、人類学に基づくデザインファーム《アトリエ・アンソロポロジー Atelier Anthropology》を立ちあげ、さまざまな企業、デザイナー、経営者と社会実装をおこなう。2023年4月より、多摩美術大学にサーキュラー・オフィスを立ち上げる。研究テーマは、「周縁」における暴力、社会的痛苦、反暴力の文化表現、脱暴力のソーシャル・デザインなど。著書に『アメリカの〈周縁〉をあるく――旅する人類学』(平凡社、2021)、『残響のハーレム――ストリートに生きるムスリムたちの声』(共和国、2015)。編著に『芸術の授業――Behind Creativity』(弘文堂、2016)。訳書に『アップタウン・キッズ――ニューヨーク・ハーレムの公営団地とストリート文化』(テリー・ウィリアムズ&ウィリアム・コーンブルム著、大月書店、2010)。
.jpg&w=768&q=100) Design and Anthropology
Design and Anthropology