
「行政」と「デザイン」。その協働の“実際”とこれから——石塚理華×富樫重太×田坂克郎×筈井淳平
行政府における「デザイン」への注目が高まっている。年齢も家族構成も文化的背景もさまざまな住民の声を聞き、地域ごとの課題に向き合わなければならないこの分野では、問題の整理や可視化、プロトタイピング、解決策の実装……あらゆるフェーズにおいて、デザイナーの力が欠かせないシーンが随所にある。
一方で、行政ならではの組織課題や制約もあり、クリエイティブ人材の登用や連携がスムーズに、あるいは柔軟に行われてきたとは言い難い側面もあるだろう。
そうした中で、“公共”の場におけるデザインの可能性を現在進行形で模索しているのが、一般社団法人 公共とデザインだ。石塚理華、川地真史、富樫重太の3名が共同代表を務めるこのチームは、自治体—企業—市民をつなぐソーシャルイノベーション・スタジオとして、各地のさまざまなプロジェクトの立ち上げや並走をしている。

- 「公共の再編」に、デザインが補助線を引くーー公共とデザイン 川地真史・富樫重太
- https://designing.jp/public-and-design
2023年10月には、初の著書『クリエイティブデモクラシー』(BNN)も上梓し、その立場をより鮮明に打ち出した公共とデザイン。そこで今回、「何がデザインなのか」を問い直すイベントシリーズ「ANY by designing #03」に石塚・富樫の両氏を招き、そのデザイナーとしての視点を行政サイドとクロスさせていくトークを実施した。
2人との対話を繰り広げたのは、渋谷区職員として今まさに公共とデザインと協働している田坂克郎と、元滋賀県職員であり、庁内有志が集ったプロジェクト「Policy Lab. Shiga」の中心にいた筈井淳平。「『行政』と『デザイン』。その協働をソーシャル・イノベーションから考える」とテーマ設定したこのトークイベントからは、多領域が混ざり合う“うつわ”としての行政府をいかにデザインの力でつくり出すか、そのヒントが見えてきた。
行政府は「盆踊り」であるべき?私と公をつなぐ“うつわ”として
「わたし」から社会を変える、ソーシャルイノベーションのはじめかた──そんなサブタイトルのつく書籍『クリエイティブデモクラシー』を著した公共とデザインは、課題解決に取り組むにあたっての、「実験、探求、共創のプロセスそのもの」を生み出そうとするチームだ。社会にある問題について多様なプレイヤーたちと一緒に考え、試行錯誤を重ねる中で、「個人=『わたし』の動機にこそ、新たな“公共”の形の糸口があると感じてきた」と、セッション冒頭で石塚は話す。
- 石塚
公共とデザインでは、課題に向き合う自治体や企業はもちろん、当事者やさまざまな住民の方を巻き込みながら、新しい生活だったり、そこにまつわる制度だったりを一緒につくっていこうとしています。今までのように誰かが新しいルールをつくり、他の人々がそのルールに従う前提では、大きな社会の変化は生み出せないと感じています。本書でも、「私はどんなことを望んでいて、どんな世界をつくっていきたいか」を一人ひとりが自らに問う重要性と、そこから自分の活動をどう社会に接続していくかについて書いています。

一般社団法人公共とデザイン 共同代表 石塚理華
その社会で暮らす一人ひとりが「自分はこういう世界を望んでいたのか」と気づき、小さな活動がいくつも生まれていく。そんな環境を支えていくような行政府とはどのような存在か、石塚はよく「盆踊り」に喩えるという。
- 石塚
おいしい屋台を準備したり、矢倉や太鼓をまん中に置いたり、集まる人に合わせて流す音楽を選んだり。住民のみなさんと楽しく踊るためのインフラづくりが、行政と私たちが今やろうとしていることです。そして、そういう場を用意した上で、「じゃあ誰が最初に踊ってくれるのか」も考える。
最初の人がすごい勢いで楽しそうに踊っていたら、それを見た次の人も、楽しく踊れるかもしれないですよね。たくさんの人が踊るようになると、それまで外で見ていた人も入ってくるかもしれません。ちょっと踊っては休んで、という人も出てくるでしょう。そうやって、一人がずっと踊り続けてなくても、いろんな役を多様な人が循環しながら担えるようになっていく。
こういう環境をさまざまな現場でどうつくっていけるか。そこにどんなセットがあれば、自分たちも含めてみんなが楽しく踊れるだろうか、ということを日々考えています。
同じく公共とデザインの共同代表であり、政策実現プラットフォーム「issues」を運営するissuesの取締役CDO / 共同創業者でもある富樫も、「個人の活動(ライフ・プロジェクト)がソーシャル・イノベーションと密接に関係している」と指摘する。地域におけるコミュニティや活動は、誰かに強いられた義務感では持続しないことを、何度も目の当たりにしてきたからだ。
では、個人の思いをどう具体的なプロジェクトに変え、共有していくのか。そこでのデザイナーの大きな役割として、「アジェンダを整理し公共化すること」があるという。公共とデザインが2022年〜2023年にかけて行った「産む」をめぐるプロジェクトは、その試みのひとつだ。

- 産まみ(む)めも展_産む物語を問い直す展覧会|公共とデザイン
- https://publicanddesign.studio/umamimumemo
- 富樫
出産をめぐる問題はこれまで、出生率、不妊治療、養子縁組といった枠組みから個別の政策や支援が行われてきました。しかし実際には、特定の枠組みだけではカバーできない課題を抱えた人もいるし、感情的なモヤモヤに向き合う機会もない。そこで、「産む」をめぐるさまざまな当事者へのリサーチを行いながら、いろんなかたちで人を集め、みんなで考えていける場づくりに挑んだんです。
このプロジェクト自体は公共とデザインが手がけたものですが、こうしたアジェンダの再公共化や、多様なステークホルダーを巻き込む際には、行政が果たせる役割の大きさを強く感じます。公的機関として、地域のさまざまな人や団体とフラットにつながっているからです。単一の課題にフォーカスする場面では企業やNPOが強みを発揮することもありますが、それだけでは限界を迎えている場面も多いですよね。
より公的なミッションを持った行政組織が、いかに“うつわ”としての機能を持ちつつ、個人の活動だけでは広がりづらい領域を政策などでサポートしていけるか。そこにデザインをどう役立てていくかを、渋谷区などと今一緒に考えています。

株式会社issues 取締役CDO / 一般社団法人公共とデザイン 共同代表 富樫重太
「マインドセット」起点のチームで、内側から行政を変える
2人に続き、マイクを握った渋谷区の田坂。メインの仕事はスタートアップのエコシステムづくりだというが、その傍らで「社会課題を解決するイノベーションラボ(=渋谷ラボ)」の構想を担当することになり、公共とデザインとの協働も推進した。
- 田坂
基礎自治体は本来、社会の課題をどこよりも吸収できているはずです。さまざまなデータも集めているし、イノベーションのための実証や実装の場もたくさん持っています。これらをスタートアップや研究者にどんどん提供することで、地域の課題が解決していくような仕組みがつくれないか。近い将来に形になることを目指して、“新しい価値観や眼差しを見つけ出し、共に実践していくために小さな実験を繰り返す実験の場”として、イノベーションラボを始めています。

渋谷区グローバル都市推進室 室長 田坂克郎
住民主体でソーシャル・イノベーションが創出されていく土壌を、長期スパンで育んでいく。公共とデザインもそのコンセプトづくりから伴走しているこの事業では、現在3つのチームに分かれて活動を行っているという。
1つ目が、具体的な課題からプロジェクトを毎年1つ実際に生み出す「実証チーム」。2つ目が、ラボで生まれたイノベーションをスムーズに社会実装するために、行政の仕組みや職員体制そのものを変えていく「行政変容チーム」。そして、中核となるプラットフォームを設計する「ラボ構想チーム」だ。
- 田坂
実証チームでは昨年はフードロス、2年目の今年は障害者雇用をテーマにしています。行政変容チームでは、急に大きな構想を打ち出すと職員に引かれてしまうので、定期的な座談会をやって少しずつ仲間を増やしてきました。ラボ構想チームでは、今後空間のコンセプト、ビジネスモデルのたたきなどをつくっていく予定です。
ただ、考えるべき要素があまりにたくさんある中で、どういう進め方がいいのか未だに悩んでばかりですね。ラボの中と外でどんな関係性でやっていけばいいか、どうしても自分の部署だけで考えてしまいがちな行政組織のマインドを変えていくか、また先ほどの例で言うところの「最初に踊ってくれる人」をどう生み出していくか……今日はみなさんにもぜひ、相談に乗っていただきたいなと思っています。
一方で、現在は金融機関に所属し、ビジネスモデルの再構築を図るチームで活動している筈井は、2015年から7年ほど滋賀県庁で働いたキャリアを持つ。その中で今回のイベントテーマに大きく関連するチャレンジに、2017年に職員有志で立ち上げた「Policy Lab. Shiga」がある。
発端は、身近な行政職員たちの声だった。想いを持って入庁したものの、本来関わりたかった業務から遠く離れた仕事をしていたり、事務分掌としてのアウトプットしかできずモヤモヤを抱えていたり。そうした違和感を筈井がまとめてSNSで改めて発信したところ、周囲から賛同の声が多く集まり、非公式な政策研究プロジェクトとして活動が始まった。
- 筈井
行政の内側に、スキルセットよりマインドセットを原動力にしたチームがあったら面白いんじゃないかと思ったんです。ちょうど当時、知事がデザイン思考に言及していたんですが、庁内にその手法を扱えるチームがなく、いい機会だと思って勝手に受け皿をつくろうと。20人ほど集まった若手職員と1年間のプログラムを組み、自分たちが幸せにしたい人は誰なのか、その人はどんな悩みを持っているのか、行政としてどう応えることができるのかを考えていきました。

『「県民の本音」を起点にしたこれからの政策形成 〜デザイン思考の活用について滋賀県職員若手有志からの提言〜』(Policy Lab. Shiga)
活動開始から1年。政策の立案からプロトタイピングまでを実践したPolicy Lab. Shigaは、「政策の起点は『語り得ない本音』にある」「部局を越えたチームで『◯◯さん』を幸せにする」「行政の都合で考えない、オープンな課題解決」「失敗を恐れず、行動しながら、答えを探し続ける」の4軸を、今後の行政組織の重要な姿勢として提言し、話題を呼んだ。
県庁にデザイン思考のプロセスを初めて持ち込んだ点もさることながら、プロジェクトを通じた個人の変革に、筈井は大きな可能性を感じていた。
- 筈井
困りごとを抱えた住民のペルソナをつくる過程で、すごく印象的な出来事がありました。ある職員が「ここまで誰かのことを考えたことはなかったし、似顔絵ができてからはこの人物に愛着すら湧いてきた。何とか幸せになってもらいたい」と言ったんです。そういう対話から生まれる内発的な動機が、新しい事業を生んでいくんだろうなと感じました。これって、まさに「クリエイティブデモクラシー」で書かれていることですよね。
本ではさらに、個人の内発性を社会につなげる存在として、デザイナーの意義も記されています。Policy Lab. Shigaでは、実はプロのデザイナーにも声をかけて、チームに参加してもらえるようにしていました。ただ他のみんなは、「デザイナーさんに入ってもらっている」という認識はさほどなかったんじゃないかと思います。立場を超えて交じり合い、お互いが同じ立場に立って絵を描き合い、一緒に変わっていこうとしていた。そのプロセスを僕らも踏んでいたことに、この本を読んで改めて気づかせてもらいました。

株式会社滋賀銀行 デジタル推進室 主任 / 元滋賀県職員 筈井淳平
行政は「決める人」ではなく「舞台をつくる人」
行政におけるデザインの重要性は年々高まっていると言えるが、実際にデザイナーが関わるうえでは、組織の特性をきちんと理解しておく必要がある。この日のトークでも、行政プロジェクトならではの難しさや可能性に何度も話が及んだ。
渋谷区の公式事業に携わるデザイナーとして、筈井の話に真剣に耳を傾けていた富樫は、クロストークに入ると、部署を超えて熱量を高めていく難しさについて率直に打ち明ける。
- 富樫
渋谷ラボなど行政との協働プロジェクトでも、少人数から徐々に始めてうねりを生んでいく重要性を感じていますが、共感の後で実際の施策に移すところが大変だと感じています。学ぶ場に行ったりリサーチをしたりして「さあやるぞ」となっても、部署に戻った瞬間に言えなくなってしまう……そんなケースは、自分自身も経験があるので。プロジェクトを通じて組織文化そのものを変えることまでしないと厳しい気がしていますが、そこはどう捉えていますか?
- 筈井
確かに、その時点で自分のチームの中にモチベーションを共有できる仲間がいるかどうかは重要です。理解のある上司がいれば何とかなるんですが、そこには運の要素もやっぱりありますから。
一方で、僕は「自分の手が届く範囲のところで、いかに変えていくか」に注力することも、結構大事だと思ってるんですね。その時すぐに変えられない対象に対して、過度に期待しすぎないこと。もちろん諦めにもなり得るので、バランスは難しいです。
聞いていた田坂も、「自分も『過度に期待すること』をやってしまっていた」と振り返る。さまざまな職員がいて、それぞれに仕事を抱えている中で、部署を飛び越えて自らと同じ熱量、同じスピード感を求めること自体に無理があった、と最近も痛感したという。それに対して筈井も、行政の「役割」について指摘しながら、こう応答する。

- 筈井
行政の仕事は、スケジュールが非常に厳しいですよね。議会が開かれるタイミングも大方決まっているので、この時期にここまでやらないといけない、というラインが明確にある。その縛りをどう突破するかが難しい。
これはPolicy Lab. Shigaではありませんが、当時自分の仕事でうまくいったかなと思う例が、多言語対応のガイドライン策定でした。通常だと、まず行政職員が骨子を作成して、有識者らによる委員会を開いてその骨子を修正・肉付けしていく、そうして仕上がったものをパブコメ(パブリック・コメント制度:意見公募手続)にかけて議会に諮る、という流れが多いのですが、最も重要なのは最初の骨子なのに、この流れでは骨子をつくる行政職員の影響力が大きくなりますよね。そこで、順序を逆転させて、県民の人たちの声が骨子になっていくように策定プロセスを設計しました。
まず県内の翻訳者・通訳者の人たちがオープンに集まり、多言語対応に対する失敗談を語り合う座談会を開く。ここに重きを置きました。座談会の内容は県のサイトで公開したうえで、その記録群からみんなで多言語対応の勘所となる論点を見つけて、ガイドラインとして編集し、パブコメにかけて議会に諮る、というプロセスを踏みました。条例に沿ったパブコメはちゃんとかけていますが、自分にとっては座談会がパブコメのようなものだったんです。
そもそも行政とは何かを「決める人」ではなく、そこに関わる人たちと共感し合えるための「舞台をつくる人」であるはず。こうした“うつわ”に徹するためのトライを考えていくほうが、行政府の人も心地いいような気がします。
行政ならではの制約はさまざまにありながらも、部署を超えた、あるいは行政と市民の垣根をまたぐ共創の扉は、実は多方面に開かれている。
筈井の話に、渋谷区で課題のステークホルダーたちと対話する場を繰り返し設けている富樫も頷き、「仲介者としての行政であり、デザイナー」として立場を共にしたいと語る。片や石塚も、成り立ちからして公益にマインドが向きやすい行政組織の特性に、デザイナーとして可能性を感じていた。
- 石塚
一般的なビジネスの場合、すでに顕在化しているニーズに対してどんどん応えていくことで、売上があがり事業が拡大していく中で、既にある社会構造を強化しやすい面があります。もちろん企業でも、新しい仕組みや関係性の創出に取り組もうとする動きは多くありますが、売上規模が大きくなればなるほど既存の事業の仕組みを、構造上の問題も含んだまま再生産してしまう傾向にある。
一方で、渋谷区の行政職員の方々と関わっていると「どうすれば暮らしが良くなるか」「まちが良くなるか」と日々考えている人は少なくなく、住民を取り巻く構造的な問題に目を向けるマインドがベースにあると思っています。職員それぞれとの会話の中でも、過去に引っかかったシチュエーションや住民の言葉を一人ひとりが具体的に思い出すことができる。そこに、なにか新しい方法につながっていくための種がたくさんある状態ではないかと、私は感じています。
「デザイナーです」とは名乗らない

“うつわ”でありながら、イノベーションの種をたくさん抱えている行政組織。その可能性を解き放とうと関わる公共とデザインの2人に対し、田坂はこの日「申し訳ない気持ちになる」とも打ち明けた。
- 田坂
(区の職員と公共とデザインの協働によって)コンセプトそのものをつくる作業がある、というのが渋谷ラボの難しいところだと感じています。それも、今回はゼロから一緒につくっていこうとしている。行政の職員には「委託先が全部つくってくれるものだ」という思い込みを持つ人も少なくありません。職員向けに「“委託”じゃなく、一緒につくるんですよ」というメッセージを何度も出してはいるつもりなんですが、そこが伝わりづらいポイントだと感じています。
これに対し、「ものすごく協力してくださっているように感じる」と返すのは石塚だ。渋谷ラボでは、行政側のチーム自体が固定化しないよう、さまざまなメンバーを交差させている。ヒエラルキーのできた、トップダウン型のチームが率いるような場に、住民とのフラットな関係によるイノベーションなど生まれてこないと考えているからだ。
とはいえ、例えば実証チームとラボ構想チームではやっていることも全く異なり、それがどうつながって新しい仕組みとして将来立ち現れてくるかも見えづらい。公共とデザイン自身も手探りななか、「かなり実感を伴いづらいプロジェクトなのに、モチベーションを下げることなく前に進もうとしてくださる人もいる」と石塚は話す。その関係性を築くポイントはどこにあるのか。
- 石塚
プロジェクトの中で意識しているのは、「デザイナーです」と名乗らないようにしていることです。もちろん本でも書いたように、人々が力を発揮する土台づくりをするのは専門家としてのデザイナーの仕事の一つだと思っています。ただそれを掲げて関わると、まさにおっしゃった“委託”の関係になってしまいますから。
- 筈井
みんなの手で描き合えるような装置を、みんなの輪の中でつくる。そんな人がデザイナーなのかな、と僕も本を読んで考えていました。デザインを民主化していくような役割を担っていると思うんです。
実はかつて僕は、デザイン面から価値を発揮できる行政職員としてキャリアを築こうとしていました。銀行に転職してからも、最初は「デザイナーです」と言えるようになりたい、と思っていた気がします。でも最近は、その肩書きを言おうとする必要がなくなってきた。それは今、デザインというものの領域がすごく広がっていることの証左なんだろうな、という気がします。銀行で僕がやっていることの本質はチームビルディングで、いかに自分たち行員の手でサービスを改善していけるか、そのための環境をどう用意するかにチャレンジしているんです。
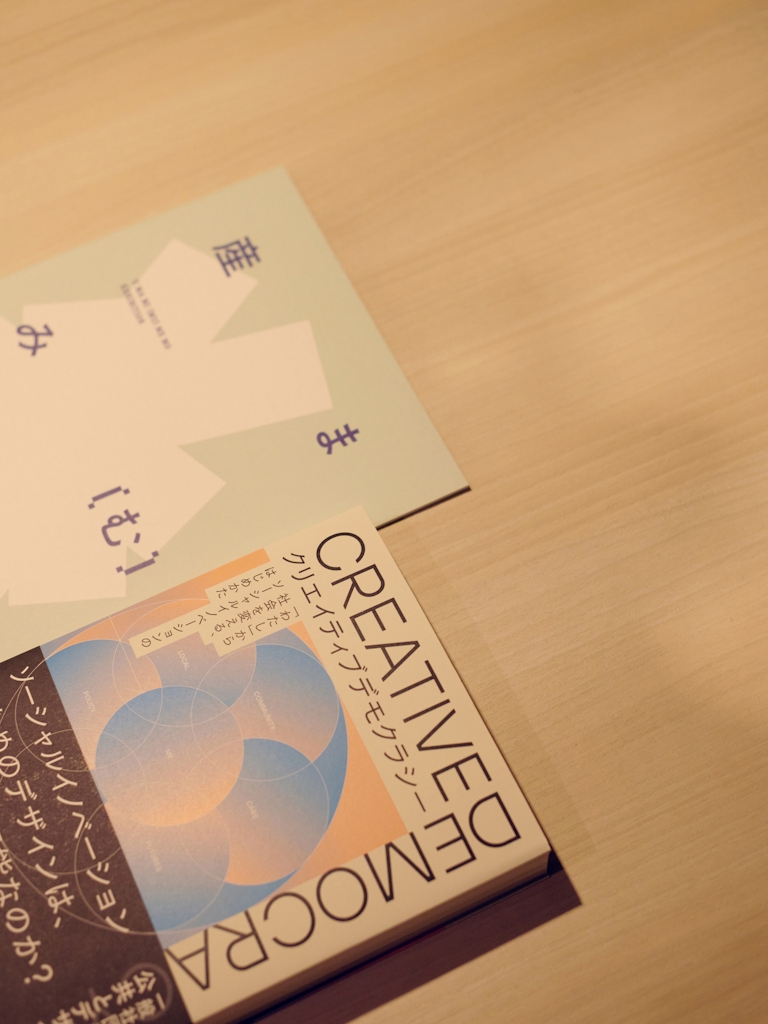
デザイナーとはあえて言わずに、チームの内側に入り込んで、同じ目線を持って関わる。「装置をつくる人」という筈井の表現に同意しながら、富樫は行政府ならではの、デザイナーの存在意義を付け加える。
- 富樫
行政においては構造的に、横断するような課題に取り組むインセンティブが生まれづらいのではないかと思います。縦割型の組織として、それぞれの課が基本計画という大きな枠組みの中で動いており、個人にも役割が割り振られているからです。
だからこそ、そこをつなぎ直していく人が必要になる。分けられてしまった状態では解決できないモヤモヤについて話し合う場をつくり、問題を可視化していくのは、デザイナーの大切な仕事だと考えています。
- 筈井
本来、それぞれの課は入口でしかないんですよね。実際の出口は何でもよくて、多文化共生の問題が、創業支援の枠組みで解決できることだってある。
ただそのためには、課題の一次受けとなった人が、自分たちだけで解決しようとせず、さまざまな課やソーシャルセクターの人々と関係性を広く持っておく必要があります。「こんな悩みを持った人がいる」という情報を共有し合える仕組みを、どうつくるかが重要ではないでしょうか。
行政×デザインの「アーカイブ」の重要性
すでにアジェンダ化されている課題、各課のミッションが明確になっているテーマに対しては、行政は強い推進力を持っていると富樫は分析する。
そこからこぼれ落ちてしまう人々に向けた、新しい解決プロセスをどう生んでいくか。田坂との出会いを、どこまで再現性あるプロジェクトにできるかできるか、渋谷ラボのプロジェクトはここからが本番となる。
- 田坂
構造的なハードルも多々ある中で、既存のルールを突破したり、新しい人を巻き込んだりしていく方法は、自分たちだけでは絶対に考えられないと思います。そしてそれは、1年やそこらでできるものでもない。実験的な意味合いも大きい中で、何度も失敗も重ねる前提で、デザイナーの方々がトライできる環境をつくっていきたいと思っています。
田坂の話を受け、筈井も最後に「失敗」について言葉をつなぐ。Policy Lab. Shigaは、プロジェクトを公式化したタイミングで筈井を含むメンバーの異動がいくつも重なり、2019年で活動を閉じていた。その過去は自身の中では「傷」になっていたというが、振り返れば後々の自らのキャリアにも生きているし、関わった他の職員のその後の活動を見ても、マインドが受け継がれていると感じている場面がいくつもあるという。
- 筈井
長い目で見る、というのは本当に大切だと思います。その中で、行政の可能性をみんなで支え合っていく必要がある。もちろん行政にも課題があって、自分たちの無謬性をもっと疑わないといけません。過去に上手くいったことばかり話しがちな一方、失敗をオープンに共有する文化があまりないのは、行政の悪いところだと感じます。もっと素直になっていけば、デザイナーや住民との協働もより生まれやすくなるはずです。
行政もデザイナーも、結局は同じ人なんです。どっちがどっちかわからないぐらいの関係になりながら、一緒にトライを続けていくことが大切で、それが今まさに現場で起きようとしているのだろうなと感じました。
- 石塚
海外のイノベーションラボやデザインラボの実践は、論文としてアーカイブが残っている場合も多いんです。どのくらいの人がどんな関わりをもって、どんな変遷を辿ったかまで詳細に載せていることもある。そうした学習の蓄積があれば、失敗を次につなげることができるし、渋谷で上手くいったことを滋賀でも起こせるかもしれない。日本中に可能性を広げる意味で、かなり重要だと考えています。
その意味で、日本での初期の取り組みとして、Policy Lab. Shigaがきちんと記録を残しているのがすばらしいですよね。変動させながら活動しているとアーカイブを残すのは簡単ではないですが、失敗も成功も、なぜそうなったかの分析があって初めてその意味を成すはず。渋谷の実践もきちんと外に公開しながら、他でも試せたり、別の地域につなげたりできるような形で展開をしていきたいです。

