
マネジメントは「空気」をデザインする——STUDIO DETAILS 服部友厚
とにかくメンバーを信じて励まし、困っていたら手伝う。その地道な積み重ねが、どこまでも質を追求するカルチャーにつながっている。
いかにクリエイティブの質を保ちながら、組織を拡大しているのか。
この問いに、「どれだけ“空気”を根付かせられるかがすべて」と服部友厚は答える。
バーミキュラやリンナイといった著名企業のブランディングを一貫して手がけるなど、その対象領域の広さと品質の高さで知られる、名古屋発のクリエイティブカンパニーSTUDIO DETAILS(以下、ディテイルズ)。2021年12月にグッドパッチのグループに参画をしたことも記憶に新しいだろう。
共同創業者でもある服部は、取締役副社長/クリエイティブディレクターとして、創業以来組織拡大とマネジメントを一手に引き受けてきた。
ディテイルズはいかに3拠点約30名のスタッフを抱え、名だたる有名企業の案件を手がけると同時に、数多の受賞歴を誇る“クリエイティブ組織”へと変貌を遂げたのか。その道筋を訊いた。
「デザイン」と距離を置いたキャリア
服部の経歴は「デザイン会社の経営者」という肩書きからは少々異色に映るかもしれない。
家業が家具やインテリアといった領域の会社だった服部にとって、デザインは身近なものだったのだろう。しかし大学卒業後は、まったく関係のないライブ企画・運営会社に就職。「いずれは家業を継ぐのだから」と、個人的に興味を惹かれた華やかな業界を選んだのだという。
何万人もの観客を動員する一流アーティストたちのコンサートを担当したが、その現場は「過酷」の一言に尽きた。ライブは土日のため、休みは基本的にない。一見、今の仕事とは関係ないように見えるが、服部はこの経験も今に活きているという。
服部「大きなコンサートでは数千人単位のアルバイトを動員することもあります。その方々に適切に動いてもらうための試行錯誤からは、本当にたくさんのものを得ました。
毎回めちゃくちゃ分厚いマニュアルをつくるんですよ。ただ、そのマニュアル通りに進めていくのが、なかなかに大変で。どう伝えれば指示を理解し、動いてもらえるかは、そこで身につけたと思います。アーティストや舞台監督といったVIPへの対応の仕方もそこで学びましたね」
ライブ運営会社を辞めてからは、家業のインテリアデザインの会社を経て、シンガポールのソファメーカーに入社。営業職として、ビジネスの基本「モノを売ること」を学んだ。

服部「家具屋の息子がメーカーに入って営業すると何が起きるのか——めちゃくちゃいじめられるんですよ。実家の競合である他の家具屋に対して、営業することになるので。僕が納めたはずの家具が次の日に外されているとか、打ち合わせをぶっちされるとか、そんなのは日常茶飯事でした。そんな中でも、数字はつくらないといけない。どうすれば仕入れてもらえるのか、試行錯誤の連続でした」
逆境の中でも努力は実を結んだ。営業成績はトップレベルになり、「シンガポール本社に来ないか」と打診も受けた。ただ、服部には「このまま会社員を続けていてもな」という迷いもあった。そんな時、ある転機が訪れる。
服部「『これからはウェブの時代が来るから、勉強しておけ』と、ある会社の社長が100万円をくれたんです。そのお金でウェブデザインとエンジニアリングの勉強をして、家具のECサイトを立ち上げました。当時はまだ、大手家具店がECに本格進出する前で、けっこう当たったんですよね。そこで高校の同級生だった海部に手伝ってもらい始めたのが、ディテイルズの原点なんです」
その頃、海部は音楽活動をしながら、自身のバンドのアートディレクターを務め、フリーランスでウェブの制作も請け負っていた。「一緒に会社をやったら面白いだろうなと思った」というピュアな動機から、ディテイルズは始まった。

- 僕らは、どうしても“質”を諦められなかった——STUDIO DETAILS海部洋
- https://designing.jp/studiodetails-kaifu
デザインスキルを重視し過ぎる潮流への違和感
こうして始まったディテイルズは、わずか数年で有名企業からのオファーが舞い込む会社へと成長。その経緯は上の記事で海部からも聞いたが、それほどの急成長を実現できたのは「幸運な巡り合わせがあったから」だけではないはず。「期待を上回る成果」を安定的に、かつ規模を拡大させながら出し続けてきたからだ。
その立役者こそ服部だろう。創業期から、「それぞれやりたいことをやって、お互いに介入しない」とは言いつつも、相方である海部がデザインに集中できるような環境を、率先して整えてきた。
服部「海部はアートディレクターなので、デザインに集中してほしいんですよ。なので、それ以外のことは、基本的に僕がやるようにしてきました。もちろん相談はしますし、大事なことは伝えますが、ノイズになるようなことは極力言わないようにしています」
意識が組織へと広がっていったのは、創業から5年が経った頃。引き合いが増え採用活動を本格的に開始してからだ。
といっても当初のディテイルズは、地方にある一制作会社にすぎない。今のように粒ぞろいの人材が集まるわけもなく、個々のメンバーと向き合う難易度は今以上に高かった。マネジメント以前に教えなければならないことも膨大にあったという。
しかし、服部が意識していたことはいたってシンプル。「根気強くメンバーと向き合い続ける」ことだけ。その根底には、「コミュニケーションこそが最も重要」という想いと「人は変われる」という信念がある。
服部「必要なときに相談に乗るとか、適切なタイミングで適切なフィードバックをするとか、そうした地味なコミュニケーションが、結局一番大事だと思っています。僕が意識しているのは、相手のことをよく観察して、ひたすらコミュニケーションをとる。それだけなんですよ」
コミュニケーションを重視しはじめたのは学生時代、和敬塾という男子寮に入寮したことがきっかけだった。
服部「そこには400人もの男子学生が生活していて、タイプはさまざまなんですけど、皆優秀なんです。そこで自分の弱さや至らない部分を知りましたし、委員長として寮を一つにまとめていこうと試行錯誤するうちに、『結局すべての問題は、話し合うことでしか解決しない』と思うようになりました」
文字にすると、至極当たり前のことにも映るだろう。
たしかに、マネジメントにおいてコミュニケーションが重要なのは言うまでもない。組織開発の分野においても、メンバーの内面性や関係性に注目しながら、対話を通して課題解決をファシリテーションする必要性は、各所で述べられている。服部は何かからインプットするのではなく、自然と実践していたのだ。
実際問題、頭ではコミュニケーションの重要性を理解していても、それが本当に実践できてる人は多くないはずだ。服部は「そもそも人に興味を持っていないのでは」と痛いところを突く。

服部「コミュニケーションって、要は相手を理解しようとすることですよね。『相手は何を考えているんだろう』と想像しながら、会話を作っていくこと。だから、ベースの部分に人への興味がないと、機能しないんですよ。表面的なコミュニケーションって、案外相手にバレてしまうので。
きっと僕は、もともと人への興味が強いし、人のことが好きなんですよね。誰かが悩みを抱えていたら徹底的に聞くし、それによって自分の時間が減ることは、全然ストレスにならない。それもあって、今のやり方になっているんだと思います」
そうして徹底的にメンバーと向き合い続けた結果、入社時はスキルも経験もなかったメンバーも、数年間で見違えるほど成長した。このことは、「人は変われる」という信念をさらに強固にした。
服部「ちょうど去年、創業期に入ったメンバーが2人、ディテイルズを卒業したんですよ。2人とも入社当時は目も当てられないぐらい仕事ができなかったけれど、エンジニアのリーダーとして数年引っ張ってくれていました。たとえどんなにスキルがない子でも、10年あればトップクラスの人材になれる。彼らは僕たちの希望なんです」
この信念は、同社が新卒採用に力を入れていることにも通底している。むしろ服部は、スキルを重視し過ぎる業界の風潮に疑問を呈する。
服部「新卒採用をしている会社がほとんどないのは、この業界のよくないところだと思っています。たしかに中途の即戦力人材を採用した方が効率はいいんですけど、それではデザインの担い手が増えない。ポテンシャルはあるけど、まだ経験やスキルがないだけの人たちの受け皿が必要なんです。会社は人を育てるための箱ですから」
伝えるのは、デザインのスキルだけでない。「月並みな表現だが、“人間力”も鍛えるべき」と言葉を続ける。
服部「人間力さえ磨いておけば、この業界で食っていけると思うんです。お客さんはデザインの専門家ではないので、デザインの質を100%的確には判断できません。それ以上に『この人と仕事したい』とか『この会社はちゃんとしてる』みたいな部分で発注していることも少なくないですから」
だからこそ、「アウトプットの質こそ最重要」という会社も少なくない中で、ディテイルズでは社会人としてのマナーやコミュニケーションを重視する。お世話になったパートナーへのリリースやお礼の連絡も徹底し、漏れていれば、ときに指摘し、ときに自ら気づかせ、メンバーの成長を促すという。
「空気」こそがクリエイティブの質を担保する
無論、服部が向き合ってきたのは個々のメンバーだけではない。チームとしての強さがなければ、規模が拡大する中安定的に高いパフォーマンスを出すことなど不可能だろう。“チームワーク”も、ディテイルズの姿勢を語る上で外せない言葉なのだ。これは、「会社として出すアウトプットはすべて全員の実績」というスタンスに表れている。

服部「特にデジタルの世界だと、一人でできることって限られているんですよ。なので、“チームでやる”文化は、けっこう大切にしていますね。例えば、ローンチ前は必ず全員でアウトプットを見るし、海部も僕もデバッグまでやります。会社全体で一つのチームなので、『自分は関わっていないから、関係ないや』とはしたくない。そういう空気は意識的につくります」
この、目に見えない文化——服部の言葉を借りれば「空気」こそが、ディテイルズの質を担保している最大のファクターである。服部は、決して上から押し付けない。「こんな品質じゃ出せない」「もっと頑張れ」というのではなく、各々が「まだダメだ」「妥協できない」と思える状態を作ろうとする。
そのために、問いかけからメンバーの主体性を引き出す。ワクワクしながらクオリティを追求する姿勢こそ服部にとっての理想だ。
服部「プロセスの順守を強制したり、マイクロマネジメントすることよりも、“ディテイルズとして出してもいいレベル”を自分たちで設定することが重要だと思っていて。『絶対妥協しないぞ』という空気感をいかにつくるかという部分が、僕が一番気を遣っているところですかね」
多くのクリエイティブワークでは、「技術のある管理者」をチェッカーに品質を管理することが少なくない。しかしそれは、管理者がチェックできる以上の仕事はできないことを意味する。
一方のディテイルズでは、メンバーの一人ひとりが判断基準を持つことをよしとする。もちろんフィードバックもあるだろうが、個々が内発的に「もっと高い品質を出さねば」と意識し、その水準が自然と高くなるようにしている。それを引き出すのが、服部の生み出す「空気」なのだ。
服部「メンバーには『60点がクライアントのOKだよ』と言っていて。お客さんと合意形成をしてからが僕たちのパーティータイム。そこからどれだけ100点に近づけられるかが勝負だよ、と伝えています」。
クライアントのOKより先に、「クリエイターとして楽しめる余白」がある。デザインという“仕事”を“楽しみ”へと転換している。
服部「『クライアントがOKと言えばOK』という人も少なくないし、これってもはや生き方の問題なので、それはそれでいいと思うんですけど。僕たちとしては、かっこいいものをつくって、インパクトのあるものを世の中に出したい。そこは妥協したくないんです」

アウトプットではなくプロセスが重要
空気感の醸成——それは、服部が苦悩の末に辿り着いた、自身の存在価値でもある。
服部「僕自身は、デザイナーでもアートディレクターでもエンジニアでもなくて。自分に何ができるのか、悩みながらトライを重ねてきました。コピーやアートディレクションを頑張っていた時期もありましたけど、どれも自分に才能があるとは思えなくて。
そんな中でも、“いいものをつくろうという空気”をつくることに関しては、唯一才能があるんじゃないかと思えたんです」
とはいえ“空気”をつくることは、目に見えるものをデザインすることより、ずっと捉えどころがないようにも思われる。そのポイントを尋ねると、「徹底して付き合うしかない。すぐにできるものではなくて、積み重ねるものだから」と、地道なコミュニケーションの重要性を繰り返す。
ディテイルズには、何度もリテイクして質を追求するカルチャーがある。ただ、これもコミュニケーションを通じて構築された信頼関係がなければ、単なる理不尽になりかねない。
服部「アウトプットにこだわっているように見えるかもしれないですけど、実はめちゃくちゃプロセスを重視していて。自分が『やりきった』と思えるところまでやれているかどうか、そこだけを見ています。そのために、『すごいいいじゃん』と言うときもあれば、不満を顔に出して『んー』って言うこともあります。ただ、そうした率直なフィードバックができるのは、お互いの信頼関係があるからなんですよ」
「おまえならできる」「最後まで粘ってくれたら、プレゼンは必ず通すから」……とにかくメンバーを信じて励まし、本当に困っていそうだったらときには作業を手伝う。そんなコミュニケーションを繰り返す。
服部「たとえ自分の業務範囲から外れていても、メンバーを積極的に手伝うことで、全体的な質も上がる。そうやって、妥協しない空気感も生まれてくるんじゃないですかね」


そんな真っ直ぐなコミュニケーションの積み重ねによって結ばれる絆は、退職時にも表出する。
服部「ディテイルズを卒業して他の会社に行ったり、独立したりする人には、『他のメンバーを育ててから抜けて欲しい』というお願いをするんです。もちろん強制力はないんですが、長い人だと『辞める』と言ってから1年半くらいは居てくれたこともありました。お互いフラットにものが言えて、相手のことを考え合えているという信頼もあるので、安心して送り出せますよね」
PMIを支える“カルチャーの番人”
こうして“質”を担保しながら組織を拡大してきたディテイルズの、史上最も大きな変化となったのが、2021年12月に発表されたグッドパッチへのグループ入りだろう。
組織が拡大し、次なるステージを模索していたディテイルズにとって、このディールは自ら望んだものだった。
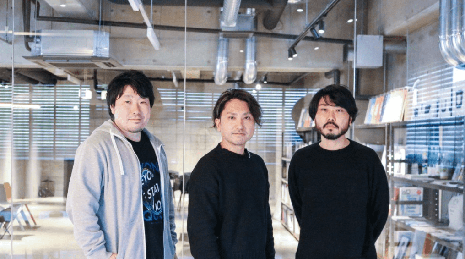
- より多くの才能の受け皿に。スタジオディテイルズとグッドパッチが目指す未来
- https://goodpatch.com/blog/future-of-studiodetails-and-goodpatch
だが、こうした大きな変化には一般的に“痛み”が伴う。それまで企業を引っ張ってきた主力メンバーたちが抜け、事実上解体というのもよく耳にする話だ。一方、ディテイルズは現状そのような危機に陥っていない。そこにも、やはり服部の手腕が大きく影響している。
服部「グループ化にあたって僕が尽力しているのは『特に何も変わらないな』と思ってもらうこと。そう定義して、対応を進めています。グッドパッチには『ディテイルズのよさを活かしてほしい』と言っていただけているし、その上でもはみ出る部分は、僕が吸収している感じですね。
今意識しているのは、これまでのやり方を極力変えずに、グッドパッチ側のやりかたに適応すること。それでも変化しなければいけない部分が出たときは、その理由を自分の言葉で伝えようと思っています。よく知らない第三者から言われると、誰しも抵抗感があると思うので」
上場企業のグループに入るからにはそれなりの変化が必要になるはずだ。経理や労務、法務や新たな業務プロセスなど、対応すべき業務は増えていくだろう。服部は、そうした変化をメンバーが感じないように対応を重ねている。
グッドパッチとメンバーの間に立つ、カルチャーの番人——そんな服部がいるからこそ、メンバーは買収されたことによって得られるメリットだけを享受し、より質の高いアウトプットを生み出すことへ集中できるのだろう。
しかし、目指しているのは「海部と服部の2人がいなくても、ディテイルズらしいものがつくれる組織」。そこに至るまでには、まだまだ道は長いかもしれない。だからこそ、プロジェクトに携わる時間を減らしても、今は特にマネジメントに力を入れる。
「1on1も全部出てみようかと考えているんですよ。鬱陶しがられるかもしれないけど」と笑う服部。その優しい表情が、すべてを物語る。どんなに優れたマネジメント論より、一人ひとりへの想いこそが力を持つのだと。

