
デジタルとフィジカル、抽象と具体……Takram「振り子の思考」が拓くデザインの可能性
UIデザイナーであってもブランド全体を考える、ビジネスデザイナーであってもアウトプットの最終的な品質感を判断する——Takramの仕事に限らず、あらゆるデザイン領域で同様なことが求められている気がするんです。
近年「デジタルプロダクトデザイナー」という職種を見る機会が増えた。
数年前まで「UIデザイナー」「UI/UXデザイナー」と呼ばれた職種に相当することが多い。
もちろん、インターフェース設計や体験設計などにも高い専門性が存在する。だが組織や企業の規模や状況においては、その「専門」のみに限らず、多様な領域を越境・横断して価値発揮することも求められる。そこでデジタルプロダクトに対し、デザインという切り口で多面的に価値を発揮する役割として、そんな肩書きを用いるようになったのだろう。
だが、この「デジタルプロダクト」という枠組みさえ、そう遠くないうちに窮屈になるのではないか。そんな可能性を示唆してくれたのが、デザイン・イノベーション・ファームTakramだ。
異なる視点を行き来する「振り子の思考(Pendulum Thinking)」を重視し、常に既存の枠組みを越えることが求められる同社。「デジタルプロダクト」「UI」という言葉を冠する職能でも、冒頭で言及したような領域以上の、越境を当然のように行っているというその現場に迫る。
異なる視点を行き来する「振り子の思考」
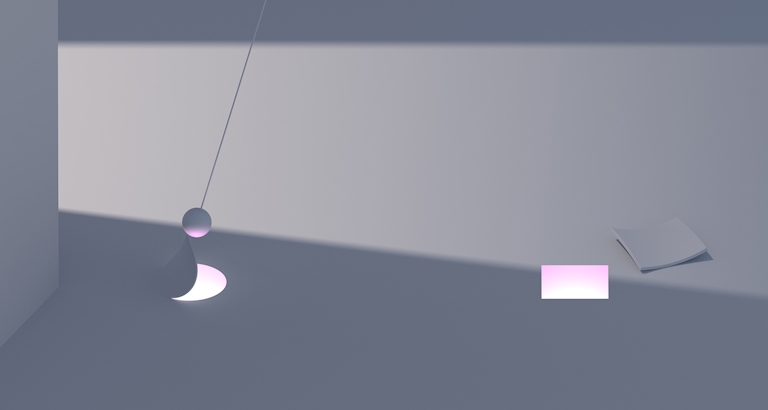
同社のMissionページにはMission・Valueに加え「Our pendulum」が記されている。
掲げるのは「異なる視点を行き来しながら、多面的に問題を理解し、分断を乗り越え、創造的発見に迫る」という言葉。つくることと考えること、抽象と具体、主観と客観、デジタルとフィジカル、論理と感性……さまざまな相反する視点から物事を捉え、その間を揺れ動き、越境することで完成形に導いていくさまを「振り子」にたとえている。
「UIデザイナーであってもブランド全体を考える、ビジネスデザイナーであってもアウトプットの最終的な品質感を判断する——Takramの仕事に限らず、あらゆるデザイン領域で同様なことが求められている気がするんです」
同社のデジタルプロダクトデザイナー 河原香奈子は、「振り子の思考」の意義をこう評する。

Takram デジタルプロダクトデザイナー 河原香奈子
この思考の好例として編集部が話を聞いたのが、中川政七商店のハンカチ専門ブランド「motta(モッタ)」のリブランディングプロジェクトだ。特にデジタル領域のデザイナーが八面六臂の活躍を見せたという。
このプロジェクトは、Takramと中川政七商店によるジョイントベンチャー・PARADEによる、コンサルティングサービスのパイロット事例としてはじまった。
中川政七商店が2013年にはじめた、「肩ひじはらないハンカチ」をコンセプトに麻や綿といった天然素材を用いてさまざまなハンカチを展開してきたmotta。だが、ブランドスタートから10年弱経ち、今後の方向性を再考する議論が重ねられていた。
リブランディングに限らず中川政七商店への統合も視野に入れていたという同ブランドの行く末を、Takramのビジネスデザイナー・佐々木康裕をはじめとしたPARADEのチームが担うことになった。

Takram ビジネスデザイナー 佐々木康裕
このプロジェクトで、佐々木が真っ先に声をかけたのが河原だった。
Takramでは基本的に挙手制でプロジェクトメンバーを決めていく。だが、佐々木はリブランディングにおいては、特にデジタルの体験が鍵を握ると考え、スタートアップでデザイナー/執行役員を経験し、デジタルプロダクトに造詣が深い河原へ声を掛けたという。
当の河原にとっても、プロジェクトへの参画は願ったり叶ったりだった。
河原「新しくプロジェクトに加わるときは、そのプロジェクトが世の中に及ぼす影響について、心から共感できることを大切にしています。mottaのプロジェクトにおいては、一人ひとりがハンカチを通じてほんの少しだけ心を弾ませて一日を始められる後押しができるんじゃないかと思って、参画を決めました。何より、わたし自身mottaを愛用していたんです。
それから“ハンカチ”と“デジタル”って、普段ならあまり結びつきませんよね。うまく融合された事例があまり思い浮かばなかったので、面白いことができるんじゃないかな、という予感もありました」
約3ヶ月かけて問い直された「ハンカチの根源的な価値」
Takramのメンバーに加え、中川政七氏やmottaブランドマネージャーなど、中川政七商店のメンバーも交えてプロジェクトチームを組成。その面々がまず向き合ったのは、ハンカチの「根源的な価値」だったという。
「そもそもハンカチとは何か?」。
一般には、吸水性や速乾性といった機能的な側面が強調されがちだが、その意義や生活における役割、使用される場面などさまざまな観点から検討。ピックアップした100を超えるキーワードを、「ニュートラル(日常的)」「リチュアル(内面に寄り添う)」「セレブレーション(ちょっとした遊び心)」の3カテゴリーに振り分け、ハンカチの持つ「情緒的な価値」を問い直していった。
河原「個人的に、ハンカチを選ぶ行為はマニキュアの色や香水の香りを選ぶことにも似ているなと感じていました。自分のために、何らかの意志を持って決めるものだなと。実際、『普段、どうやってハンカチを選んでる?』と議論を重ねてみると、ハンカチを持つときは、ほんの少し気分をととのえたい日じゃないか、という一つの方向性が見えてきました」
もちろん、その成り立ちにも立ち返った。「ハンカチを選ぶ時間は今日の気持ちに向き合う時間」「どんな気持ちも肯定する」「今日一日を過ごすため、新しい気持ちをサポートしてくれる存在」といったキーワードを出し合い、それを傍らに議論を重ねる。
すると、徐々にハンカチの持つ「根源的な価値」への解像度が高まっていったという。例えば佐々木は「ハンカチを選ぶ瞬間、『今日はどんな気分かな?』と自分と向き合う時間を与えられていると気づいた」という。
そうして約3ヶ月にわたって議論を繰り返し、ブランドとして掲げるものを改めて言葉へ落としていく。結果生まれたのが、新たなブランドビジョン「昨日、今日、明日。新しい気持ち。」と、ブランドコンセプト「リズム、ととのう、ハンカチ。」だ。

ブランドビジョンとブランドコンセプトのほか、インナー向けにブランドミッション「新しいハンカチ文化をつくる」、ブランドパーソナリティ「ととのっている時の、わたし」を設定。プロダクトやウェブサイトなどを形にしていくための判断軸となるブランドコアを言語化した
あわただしく身じたくする朝、ハンカチを選ぶ瞬間に自分と向き合い、今日の気分を問いかける。昼食後に軽く息を抜き、ハンカチを畳みなおす……一日の中で句読点を打つように、ハンカチを持つシーンをイメージして、河原も佐々木も職種関係なく議論にコミットし、ブランドの根幹を再定義した。
商品企画、価格、香り……デザインが行き来する領域
約3ヶ月の「考える」フェーズを経てブランドの軸が練り直した後は、その実装を進めていく「つくる」フェーズへと移行した。
そこでチームへ加わったのが、デザイナーの長谷川昇平だ。博報堂アイスタジオを経て2015年にTakramに参画、以降はUIデザインを中心にKINSやORBISなどプロジェクトを手がけてきた。
EC機能を含めてWebサイトをリニューアルするにあたり、河原とともにUIデザインを担うこととなった。
長谷川「リブランディングを行うにあたり、デジタルの接点であるECでも、mottaらしい世界観はどのように表現できるかということをチームで議論しながら進めていきました。
香りや刺繍とともに楽しむことのできるハンカチブランドを実現するには?機能性に偏りすぎない、ちょっとした遊び心(セレブレーション)を感じる世界観を実現するには?性別に偏りすぎないニュートラルなデザインのバランスは?……そんな議論を重ねていましたね」

Takram デザイナー 長谷川昇平
ただ、Takramの面々が関わる上では「単に作る」ということはない。
ロゴやパッケージ、プロダクト、Webといった制作物を形にするにあたっても、たびたびブランドの軸となる部分へと立ち返り議論を重ねた。「考える」と「つくる」、抽象と具体を行き来し、手を動かしながら思考を深めていく──。
その思考を象徴するようなアウトプットが、mottaの新たな商品カテゴリーでもあるハンカチに吹きかける香水である「ハンカチパフューム」だ。
初期のコンセプト策定のフェーズで出てきた「香り」というキーワード。ハンカチを選ぶように、気分に合わせて香りを選べたら……というアイデアから、ハンカチのみにとどまらない新たな商品企画も立ち上がった。
ハンカチを単に「手を拭うもの」ではなく「一日一日に寄り添ってくれる存在」と定義。生地に吹きかけることで広げるたびにふわりと香り、気分を切り替えられるという、ハンカチによる新たな体験を提示した。まさに「リズム、ととのう、ハンカチ。」を体現するプロダクトだ。
河原「みんなでパフュームの香りを試し、香りの調合や名付けを考えていきました。香りというインターフェイスをいかに表現して、ブランドコンセプトに沿ったものにするか……それも含めてデザインだと考えました」

河原と長谷川はほかにも、他職種のプロジェクトメンバーや中川政七商店サイドのメンバーと協働しながら、多様な領域を越境していく。
例えば、商品やラインナップの開発。中川政七商店のプロダクトデザイナーが提案した新作「ある一日のハンカチ」では、折り方によって色柄の出方が変わることで、一日のうつろう時間を表現。オリジナルフォントやモノグラムといったイニシャルやモチーフをすべてのハンカチに入れられる「オーダーメイド刺繍」など、布地から検討し、ブランドコンセプトに即したプロダクトやサービスも加わっていった。
こうした商品開発は中川政七商店を中心に進めていったが、両社メンバーともに「デジタルとフィジカル、企画や戦略から実際にお客さまの手に届くまで、一貫して携わった」と河原。
価格設定もそのスコープのひとつだ。1枚あたり1,500円〜2,000円ほどの価格帯であるハンカチは、それ単体ではギフトにしては少し物足りない。それゆえ、約3,000円のパフュームを合わせてセットにする……そうした領域は、もはやデジタルデザイナーのそれを軽々と超える。
長谷川「商品開発や価格設定、ラインナップなどについて議論しながら、それをUIに落とし込んでいく。ユーザーとの接点であれば、商品名でも香りでも、あらゆる“UI”をデザインするんです。かつ、それが事業上の成長にもつながらなければいけない。さまざまな『つくる』と『考える』を行き来していました」
「振り子」だからこそ生み出せた成果
こうして2021年11月にリスタートしたmotta。リブランディングの結果、ハンカチパフュームとのセット売り、オーダーメイド刺繍といったギフト提案やまとめ買いに適したラインナップが奏功した。佐々木が重視していたデジタルの体験を中心に好調な滑り出しを見せているという。
この成果も、Takramゆえの「振り子の思考」の影響が大きい。
長谷川「今回、僕は『つくる』フェーズから入りましたが、ここでコンセプトを単に共有されるだけでは、作業的な仕事になりかねません。でも手を動かしながらもコンセプトに立ち返り議論しつつ開発を進めていたので、事業やブランドに対する理解や解像度が高まる。
抽象での理解が深まると、具体の精度も上がってくる。mottaであれば、ハンカチの存在意義や役割を理解するからこそ、こんな情報や機能が必要だと気を配れたりするんです」

こうした行き来は、デジタル⇔フィジカルでも同様だ。「単にWebサイトをデザインするだけでなく、ブランド全体をいかに構築していくかを議論しながら、デジタルとフィジカルの体験を複層的に作ってきた」と佐々木。
例えば、たまたま店を通りかかった人がmottaを購入した時、そこからいかにデジタルのタッチポイントを作っていくか。SNSのフォローなどを促し、公式サイトから記事を配信し、次なる購入へとつなげていく……。そういったアイデアを、ときにはプロトタイピングしながら議論し、デジタルとフィジカルの双方で設計・展開してきた。
河原「抽象の議論を重ねている中でも『こんなメッセージが良いのでは?』と、自分で写真を撮り仮の記事を作ってみたり、ブランドのコアと照らし合わせながらサイトのラフなデザインを作り、『こんな感じですか?』とディスカッションの土台にしたり。抽象の議論であっても、具体を見ながら話すことを意識していましたね」
佐々木「どんなにロジカルでかっこいいコンセプトを打ち立てても、具体的なアウトプットが見えてこなければ議論は深まらない。コンセプトは、建物で言えば基礎のようなものでしかありません。そこに骨組みをつくり、どのような建物を建てていくか、それぞれを考え続けなければよいアウトプットは生まれませんから」
私たちは当たり前のように目的に応じてSNSを使い分け、ストレスなく動作するサイトをスクロールし、アプリをスワイプする。そういったデジタルでの体験が担う役割が大きくなるほど、フィジカルの体験が担う要素はより先鋭化し、逆説的に重要性も増す。
これはデザインにおいても同様。具体のインターフェースがコモディティ化し抽象レイヤーの戦略や思想の重要度が増せば増すほど、そ れを反映するインターフェースの重要度や実装難易度も高まる。
ゆえに、デジタルとフィジカルを、抽象と具体を、つくると考えるを行き来しながら、専門性の「深さ」と「広さ」を兼ね備えたデザイナーはますます重要になるのではないか。

- UIデザイン×Takramについてお話ししませんか?
- https://meety.net/matches/nWmpVGyAUJtt

- TakramのUIデザインの裏側についてお話しします
- https://meety.net/matches/fZEJcidacMce
