
デザイン思考が生んだ、問題解決というデザインの「誤解」
イノベーションを促進する方法として、2000年代のビジネス界に瞬く間に広まった「デザイン思考」。しかし、そのなかで「デザインは問題を解決するためのもの」という誤った意識が強まってしまったと、あるデザイナーは警告する。
アップルの台頭とともに高まった企業のデザインへの関心。
その流れを追い風に広まったのが「デザイン思考」ではないだろうか。
しかし、そのなかで「デザインはアップルの成功を追随させてくれるもの」「デザイナーは問題を解決する人」という認識も強まってしまい、デザイナーの役割を窮屈にしててしまった——ノースカロライナ州立大学グラフィックデザイン学科助教授で、自身もデザイナーのジャレット・フラーは言う。
では、デザイナーの真の力を発揮するためにもつべきマインドセットとは何か? フラーはスウェーデン政府イノベーション庁「Vinnova」の元ストラテジックデザイナーで、現在はメルボルン大学デザイン学部長を務めるダン・ヒルの言葉を引用し、「文化の発明家」としてのデザイナーのありかたを説く。
以下、フラーのブログ投稿『What if design isn’t problem solving?』を、公式な許可のもと翻訳した。
米ビジネス誌『Fast Company』の編集者であるスザンヌ・ラバールが、「Why Corporate America Broke Up With Design(なぜアメリカ企業はデザインと決別したのか)」という非常に興味深い記事を書いている。私の興味を引いた一節を、少々長いがその価値があると思うのでここに引用する。
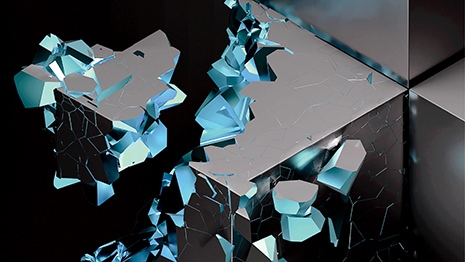
- Why corporate America broke up with design
- https://www.fastcompany.com/90779666/why-corporate-america-broke-up-with-design
もしスティーブ・ジョブズが率いていた頃のアップルが企業にとって手が届かない理想形なのだとしたら、デザイン思考とはその対極にある誰もが手を出しやすい存在だったのだろう。シリコンバレー生まれのデザインコンサルティングファームIDEOと共に広く知られることになったデザイン思考は、デザイナーたちが常に行なってきた「顧客とそのニーズを理解する」という作業を企業も行なえるようにするためのプロセスだ。
重要なのは、これによって「解決策を考え、それを検証する」という科学的手法の要素が、利益追求型の新しいアイデアを追及する非科学的な営みに持ち込まれたことである。「簡単にできるがゆえに、山火事のごとくアメリカのビジネス界に広まった」と、サンフランシスコのデザインファームNewDealDesignの創設者ガディ・アミットは言う。
その最盛期、IDEOには針を使わない注射から「プリングルズ」の改良まで、ありとあらゆる依頼が殺到した。2000年代の同社のクライアントといえば、アンハイザー・ブッシュやGAP、HBO、コダック、マリオット、ペプシ、PNC、メイヨー・クリニックなど。食品からアパレル、金融、医療と実に多岐にわたっている。P&Gの洗剤ブランド「Mr Clean」のために「マジックリーチ」という大ヒット商品を生み出したのもIDEOだ。壁いっぱいに付箋を貼り付けるスニーカーを履いたクリエイティブな人々というイメージを、IDEOは長年スーツにネクタイ姿でスプレッドシートを睨んできた企業に刻みつけた。
しかし、デザイン思考は魅力的である一方で、それが必ずしもポジティブな結果を生み出すとは限らなかった。UXデザイナーで『User Friendly』の共同著者(さらに元『Fast Company』の編集者)であるクリフ・クアンは「人々は『すべてのプロセスを経たのに、なぜビジネスが好転しないんだ!』と言っていましたた」と、語っている。
クアンは、2012年に初のCDO(Chief Design Officer)を雇い、社内デザインチームを設立したペプシコを例にあげ、デザインへの投資によって大ヒット商品が次々と誕生するわけではないことを指摘した(炭酸飲料界のiPhoneが生まれていなことは確かだ)。例えば、ソフトドリンクの売り上げ減少の対応策として生まれた、水筒と一緒に使うカプセルタイプの商品「Drinkfinity」は念入りなデザインプロセスと試作品テストを経て、大規模なプロモーションと共にリリースされたが、2018年の発売からたった2年で製造中止というあっけない結末を迎えた。
クアンは言う。「何が市場で成功するかをデザインが決めることなどほとんどありません」
ラバールの記事は、すぐに指導している学生たちへの課題にしようと思ったほどインパクトがあった。
それは記事の意見に全面的に同意したからではなく(同意するところは多いが)、今日のデザインにおいて当たり前になってしまった考えに疑問を投げかける内容だったからだ。まだ私の考えも完全にまとまったとは言い難いが、以下に特に強く感じた考えをまとめる。
アメリカのビジネス界にとって、デザイン思考はアートと商業のバランスをとる術だった。IDEOのCEOティム・ブラウンが20年も前に『ハーバード・ビジネス・レビュー』にデザイン思考に関する寄稿をしているが、その内容はデザインがいかに企業の売り上げに貢献できるかを売り込むものだった。当時はアップルが頭角をあわらし始めた頃で、企業はどこもデザインというものを欲していた。そしてデザイン思考は、アップルの成功を追随させてくれる術だという印象を与えたのだ。
しかし、それから20年が経ったのち、ようやくデザイン思考にも批判的意見が出始めた。ニューヨーク大学の教授ナターシャ・イスカンダルの『ハーバード・ビジネス・レビュー』への寄稿「Design Thinking is Fundamentally Conservative and Preserves the Status Quo(デザイン思考は、基本的に保守的であり現状維持にすぎない)」、デザイナーのダーリン・ブゾンによる「Design Thinking is a Rebrand for White Supremacy(デザイン思考は白人至上主義のリブランドである)」、カルチャー誌『n+1』に掲載されたデザインリサーチャー、マギー・グラムの「On Design Thinking」などがその例である(私ですら『Design Observer』の2019年の記事「Against Design?(デザインに反対?)」でこの動きに加わった)。
私が思うに、これらの記事が訴えているのは、商標としての「デザイン思考」は結局ただのマーケティング用語に過ぎなかったということだろう。実際に機能するわけではないのだ。そして、今日に広く知られたプロセスとしてのデザイン思考もまた、自称“解決策”を継続的に生み出してはいるが、その解決策自体はそれほど革新的でも刺激的でもなく、文化的意義もない。デザイン思考がしていることと言えば、それを採用している企業の懐を温めることくらいなのではないか。
デザイン思考における「ユーザー中心設計」は、いっそ「企業中心設計」と呼んだ方がわかりやすいだろう。デザイン思考によって”解決”される”問題”のほとんどは、いかに利益を上げるかなのだから。
奇しくもラバールの記事を読む数日前、メルボルン大学デザイン学部長であダン・ヒルの素晴らしいインタビューを聞いていた。このなかでダンは、「問題解決としてのデザイン」について苦言を呈している。「正直なところ、私たちは問題解決に長けているわけではありません」とヒルは言う。「デザイナーが実際にしているのは文化的発明です。新しい物事を生み出すことであって、それは問題解決とは異なります」
私が気に入っているのは、ヒルがデザイナーを文化の発明家と定義しているところだ。
問題を解決する人と言われるよりもずっと魅力的に聞こえる。しかし、この定義で最も素晴らしいのは、デザイナーの視点に再び余白を与えてくれる点だ。ラディカルな決断、予期せぬイノベーション、文化的意義のための余白を与えてくれるのだ。
なにも「作家としてのデザイン」や「天才デザイナー」の神話に戻ろうというのではない。もちろん、最高のデザインは、常にユーザーや観客を尊重している。ただ、ユーザー重視だからといって、自分たちの作品を見せるなということでもないのだ。この点については、プロダクトデザイナーであるフランク・キメロのブログ投稿を引用したい(この投稿は現在消えているので、「archive.org」を通じて取得した)。
デザインは、その価値を示すのに派手である必要はないが、目に見えないのもよくない。デザイナーの危うさは、見えないことをエレガントだと勘違いしたり、単純さを明確だと誤解したりするところにある。優れたデザインとは、ただ理解されるためだけでなく、ユーザーに愛されるように心に訴えかけるものだ。ただ明確に印象的だったという理由で感銘を受けるようなものがあったとしたらどうだろう?なぜそういうモノを作ろうとするのが、悪なのだろうか?
スティーブ・ジョブズがトップだった頃のアップルは、ユーザーテストをしなかったというのは有名な話だ。デザイナーたちは、新たなインタラクションのアイデアや、製品が何をすべきでどのような感触を与えるべきかに関するゴールなど、自身の見解をもってプロジェクトに携わった。そして、そうしたアイデアはそのままプロダクトに反映されたのだ。
アップルで長年デザインを率いたジョナサン・アイヴは、デザインは目に見えないものであるべきだというディーター・ラムスの言葉をよく引用していた。しかし、実際のところ、アップル製品におけるデザイナーはかなり目に見える存在である。ドライブや物理ボタンをなくし、端子や充電器を変え、新たなインタラクションや作業の方法を生み出すといった革新的な決断は、良くも悪くも厳格なデザイン思考のプロセスを経たものではなく、デザイナーの強い意見によって実現に至ったものだ。
キャンディカラーのiMacや、真っ白なコードのイヤフォンがついたiPod、iPhone、AirPods──。アップル製品やジョブズがつくったものについてあなたがどう思おうと、同社がリリースした製品はどれも他に類を見ない象徴性をもち合わせている。文化を形作るこうした製品は、デザイン思考からは生まれない。ラバールの記事で、クリフ・クアンは文化的意義をもつ可能性をもちながらも、いまひとつ成功していないものの例として「Kindle」を挙げて説明している。
「デザイン思考の居場所は、デザインというもののどこかにはあるのでしょう。それをまるごと否定するつもりはありません。ただ、デザインがエンジニアリングのようになりすぎると——つまりデザイナーが文化の発明家ではなく問題を解決する人になってしまうと——そもそも私たちがデザインに興味をもつきっかけになったスキルすらも失ってしまう可能性があると私は言いたいのです」
『ニューヨーク・タイムズ』のアップル担当テック記者であるミックル・トリップは、著書『AFTER STEVE アフター・スティーブ―3兆ドル企業を支えた不揃いの林檎たち』(ハーパーコリンズ・ジャパン)の中で、ジョブズ亡き後のアップル社内に生じたデザインと実務、アートと商業の間の確執について触れている。
トリップが言うには、ジョブズはビジネスや最終目標を見失うことなくデザインに関する鋭い決断を下すことができるユニークな立ち位置にいたという。ジョブズの死後そのバランス役がいなくなり、デザイナーは視野が狭まり、実務側はコストとプロセスを重視し、両者がともに過度な指標をもちはじめたのだと指摘する。
ジョブズの有名な言葉で「アップルは、テクノロジーとリベラルアーツの交差点にある」というものがある。ここ10年、デザインはテクノロジーにより過ぎて、リベラルアートの側面をおろそかにしているのではないだろうか。
Macと出会ってデザイナーを志したという人はたくさん知っているが、Kindleがきっかけでデザイナーになったという人には会ったことがないように思う。あなたは、どう考えるだろうか。
