
「つくる」を復権させるために。必要なのは、手を動かし続けること──VUILD・秋吉浩気
ものづくりを通して、僕たちは自分らしさやアイデンティティを見出す。あるいはそれに気づいていく。そうした文化を僕たちは取り戻していきたいんです
Cover Storiesアイデアとラップトップさえあれば、どんな子供でも世界を変える企業の種を生み出せる──そんなフレーズが高らかに叫ばれたのが、2012年。デジタルのものづくりによる革命を謳い、「メイカーズムーブメント」を牽引する引き金となった、クリス・アンダーソンの著書『MAKERS』の一節だ。
デジタル技術の発展とそれを活用したツールの普及が、「つくること」を民主化し、ものづくりの世界を大きく変革する……2010年代前後に期待された未来像は、約10年が経過したいま、果たしてどれほど実現されているのだろうか?
2010年代から一貫して、「つくること」の民主化に向き合いつづけてきた人物がいる。デジタルテクノロジーによって建築産業の変革を目指すVUILDの代表取締役CEO・建築家/メタアーキテクト、秋吉浩気だ。
秋吉は日本におけるデジタル・ファブリケーションの第一人者・慶應義塾大学SFC田中浩也の研究室出身であり、デジタル・ファブリケーションの技術をコアに、内装・住宅・建築領域において「建築の民主化」に挑戦してきた。
創業前は3D木材加工機「ShopBot」を使って子どもと一緒に「自分が遊びたい遊具をつくる」ワークショップを実施する活動などを重ね、創業後は「ShopBot」の販売導入や、設計から木材加工までをワンストップに完結できるオンラインツール「EMARF」をはじめとする複数事業を展開。それと同時に、内装・空間・場をつくるクリエイティブチーム「VUILD Place Lab」や次世代建築を開拓する建築集団「VUILD ARCHITECTS」を創設。2022年にはデジタル家づくりサービス「NESTING」もローンチした。
そして、VUILDは2023年10月にCIを改訂し、2027年に向けたミッションを「つくる伴走者をつくる」に再設定した。人々がものづくりをする環境までつくる“メタアーキテクト”と呼ばれる人々を増やしていくことを目指す秋吉。氏の目には、新技術が次々に登場する現代における、「つくること」の現在地はいかに映っているのだろうか?
失われた「つくる文化」を取り戻す

取材班が向かったのは、神奈川県・海老名市のVUILD工場。
何の変哲もないロードサイドにある建物に入ると、木の切断音がけたたましく鳴り響き、粉塵を除去する巨大ダスターが轟々と音を立てていた。ずらっと並んで置かれたカット済み木材は、瀬戸内海の島へと明日発送予定だという。
内装・住宅・建築領域……現在はさまざまな事業を多角化展開するVUILDだが、出発点は、木材用3D加工機「ShopBot」の販売導入だった。
創業以前、ShopBotを活用した子ども向けワークショップを個人で手がけていたことが、「つくること」の民主化に懸ける想いの根底にある──自らのルーツを振り返りながら秋吉は語る。
秋吉「VUILDの原点は、子どもがつくりたい遊具を木工3Dプリンターで一緒につくるワークショップでした。知識もスキルもない子どもたちが、自らの手で遊具をつくり、『私が考えたオモチャだ!』と喜んでいる。その親御さんも、夢中に子どもが遊ぶ姿を見ながら『この子や孫が大人になる頃には、ものづくりの未来の常識は変わっているはずです』と説明すると、喜んで聞いてくれる。そうした姿を見ていて、『これは社会が変わるなな』と感じたんです」
そこから現在に至るまで、一つひとつの事業やプロジェクトを試行錯誤で進めてきた。
ShopBotの販売導入に加えて、設計から木材加工までをワンストップに完結できるオンラインツール「EMARF」を開発。それと並行して、ShopBotを活かして内装・空間・場をつくるクリエイティブチーム「VUILD Place Lab」や次世代建築を開拓する建築集団「VUILD ARCHITECTS」を創設する。
さらに、家具や構造物をつくってきた経験を活かして、富山県南砺市利賀村で設計・施工をした〈まれびとの家〉は2020年度グッドデザイン金賞を受賞。2022年には予めカットされたパーツを組み上げるだけで家をセルフビルドできるデジタル家づくりプラットフォーム「NESTING」をローンチした。
こうした取り組みは、ものづくりの「祝祭性」や「楽しみ」、ひいては個人の“美学”を取り戻すことにもつながるはずだと秋吉は語る。

秋吉「NESTINGは、自分で家をつくる営みを取り戻すサービスです。本来、家を建てるという行為はお祝いごとであり、ありがたくい、楽しいものだったはず。しかし、いまは自分が住む家づくりのほとんどを外注している人が多いから、その実感が失われているように思えます。
本来、自分の家をつくることは、自分の個性を表現するつくっていくことでもあったはずなんです。たしかに誰かがつくり込んだったホテルや貸別荘に一時的に泊まり、お洒落なライフスタイルに染まることはできますが、それは“暮らし方”ではありません。ものづくりを通して、僕たちは自分らしさやアイデンティティを見出す。あるいはそれに気づいていく。そうした文化を僕たちは取り戻していきたいんです」
では秋吉にとって、個性や自分らしさが宿る「文化」とは何か。それはブランド品のように誰かに認められた価値を持つもので身の回りを固めるのではなく、あくまで自分らしさが滲み出るものと生活をともにすること、それをつくり出すことではないかと語る。
秋吉「例えば住まいに置く家具ひとつとっても、自分が本当に美しい、好きだと思えるものを置くことが大切だと思うんです。それが自分の美の基準や価値判断を持つことであり、そこに自分の個性や価値観が宿る。誰かの“お洒落”や“かっこいい”を受け入れるだけでなく、本当に好きだと思えるものをつくることを通してこそ、暮らしは豊かになっていき、生きている実感が湧いてくるのだと思います」
技術それ自体では価値はない。

コンピューター制御により、木材を正確かつスピーディーに加工して切り出せるCNCルーター「ShopBot」。2013年から秋吉は国内唯一のエバンジェリストとして販売導入を進めている
そうした「つくる」文化の盛り上がりは、2010年代に盛り上がりを見せた「メイカーズムーブメント」や「デジタル・ファブリケーション」にも見られたと言えよう。
しかし、いまやこうした言葉は、ずいぶんと耳にする機会が少なくなったようにも感じる。
新しく登場した流行りの技術は、ともすれば“バズワード”として扱われてしまう──「デジタル・ファブリケーション」もそうしたプロセスをたどった言葉の一つとも言えるのではないか。新技術がバズワード化し、トレンドに飲み込まれて“飽きられて”しまうことについて、「技術論的な考え方だけでは新技術は普及しない」と2020年当時に秋吉は語っている。その技術で何ができるかではなく、それを使うことでどう暮らしが変わるのか、どんな体験が届けられるのかまでパッケージすることが大事なのだと。
秋吉「技術はそれ自体に価値があるというよりも、技術の要素同士をつなげて一つの体験や物語、デザインにまで仕上げることに意味がある。デジタル・ファブリケーションに長期にわたって向き合うなかで、そういった当たり前のことに気づいたんです。
初期デジタル・ファブリケーションの課題は、一部の技術オタクやギークの人の間のブームにとどまって、デザインやライフスタイルの領域にまで浸透できなかったことではないでしょうか。新しく生まれた技術をアートや芸術、文化へと接続させなければ、『つくること』の民主化は先に進まないと思っています」

重要なのは技術ではない。それがいかに私たちの文化や生活、暮らし方を変えるか──こうした観点から思考を積み重ねて生まれたのがNESTINGだった。培ってきた技術的な蓄積をもとに、ユーザーからの需要があり、スタートアップ的な成長を見込める領域を模索。その結果、セルフビルド型の住宅が反響・手応え大きく、型を磨き上げればスケーラブルな事業になることがようやく見えてきた。
秋吉「NESTINGは、家を建てたことのない素人にもわかるように、技術をパッケージ化して一つのブランドにしたものです。『つくること』の民主化によって家づくりや暮らしがいかに変わるかを訴求したいという想いから始まりました。単に家を建てたい人というよりも、『拠点を自分でつくって暮らしたい』という欲求を持つ人のライフスタイルを変えるツールだと思っています。
VUILDは当初ShopbotやEMARFを中心に活動してきましたが、僕たちには長い時間をかけて蓄積された技術や経験があります。それらを〈まれびとの家〉のような建築事例やNESTINGなどの事業やプロジェクトに落とし込むことで、さまざまな手段を用いて民主化を目指すフェーズが、いままさに訪れています」
あらゆる職業は「メタ」的になる──これからのデザイナーの役割

技術の発展は誰でもものづくりができる世界をもたらす。だが、身の回りにある生活や文化にまで浸透しなければそれは普及しない。
私たちの身の回りに存在するデザインのあり方が、社会的・経済的背景や技術の変化と不可分なのだとすれば、こうした変化に既存のデザイナーはいかに向き合えば良いのだろうか。
前掲の『MAKERS』の4章に付けられた「僕らはみんなデザイナー だれでも上手にデザインできる時代がやってきた。」というタイトルは、そのヒントを示唆しているように思える。すなわち、「つくること」の民主化が実現した未来では、誰もが創造性や自分らしさ、アイデンティティを引き出せる世界を実現するという未来予測だ。
そうした未来において既存のデザイナーは、「デザインする人」ではなく、ツールを通じて「デザインする力を与える人」になるだろうと秋吉は語る。そして、この変化を「あらゆる職業は『メタ』的になっていく」と表現する。
2022年に上梓された秋吉の書籍『メタアーキテクト──次世代のための建築』によれば、「自らを客観視することで高次の次元に到達し(メタ認知)、代謝を繰り返すことで(メタボライズ)、変貌(メタモルフォーゼ)を遂げる」という想いが「メタ」という言葉に込められている。
そして秋吉の肩書には「建築家/メタアーキテクト」と記されており、自ら建築家として手を動かしてつくりながらも、その技術を他人にも分け与える、新たな建築家像として「メタアーキテクト」が提示されているという。では、具体的にはメタアーキテクトが目指す世界観とはいかなるものだろうか。
秋吉「ShopbotやEMARFは使いはじめる敷居が低くて、少し器用で興味がある人であれば誰でも仕事のひとつにできると思っています。例えば、VUILDがEMARFの普及活動を行ううちに、家具などをつくれる人が増えている。あるいは、NESTINGで家をセルフビルドした施主が使い方を覚えてしまう。
すると、その『最初に試してスキルを身に着けた人』がメタな存在となって、周囲にいる人を指導したり、プロジェクトをサポートしたり、あるいは自分がDIYの専門家として活動したりできるようになります。もちろん、プロにまでは達しませんが、こうして抽象化された職能として『メタ』な存在が出てくるはずなんです」

メタアーキテクト、あるいは「メタデザイナー」は全てを自ら手掛けようとせず、“デザイン支援者”としてデザインの力を分け与えようとする。クライアントワークにおいても、自分がつくるのではなく、相手につくり方を教えてサポートする。そうすれば、従来までクライアントワークで1人に対して使っていた時間で、10人、100人のやりたいことが叶えられるかもしれないと秋吉は語る。
秋吉「デザインする側/される側の関係性や立場が、技術によって揺らぐことで、さまざまな可能性が広がると感じます。『メタ』な職業がリアリティを増すなかで、まずはVUILD自身が率先して『メタ』な建築家やデザイナーの役割を担い、他人に演じて再現してもらうのがこれからのフェーズになっていくと思います」
メタデザイナーの核心は「誰かのためにつくる」こと
こうした考えから、2022年にVUILDでは「EMARF CONNECT」というコミュニティを実験的に開始した。EMARFの使い方をVUILDメンバーが直々に教えるコミュニティだが、それだけでは「メタ」な職能としては成立しないかもしれない……「つくること」の民主化を推し進めるためにもう一段階必要な要素を、秋吉は実際に活動するなかで感じたという。
秋吉「EMARFの使い方を教えると、みんな自分がつくりたいものを、自分のためにつくりはじめます。EMARFユーザーの中には建築家やデザイナーのユーザーも多く、それによって素晴らしいものが生まれることも少なくありません。しかし、僕はそれだけでは『メタ』的にはなりづらいと思うんです。
たしかに『こういうものを自分が作りたい』『こういう表現がしたい』という自己表現欲求に基づく創作は、世界を豊かにします。ただそれだけでは、自分たちの力で何かをつくっていこうとする文化はなかなか広がらない。
僕が考えるメタデザイナーとは、江戸時代の大工のように、『誰かのためにこれをやってあげる』という姿勢を持っている人です。内側の思考に向かうのではなく、もっと自分の力を活かせないかと外に目を向けてみる。そして、『自分にはこれができるので、誰かのつくりたいものを翻訳をできます』と、一緒につくることを導ける人が必要なのだと思います」
誰かに「つくる力」を分け与えるメタデザイナーの仲間を増やしていく。かつ、EMARFのような技術を提供して援護射撃していく。そうすることで、ようやく世の中を変えていけるのではないか、と。
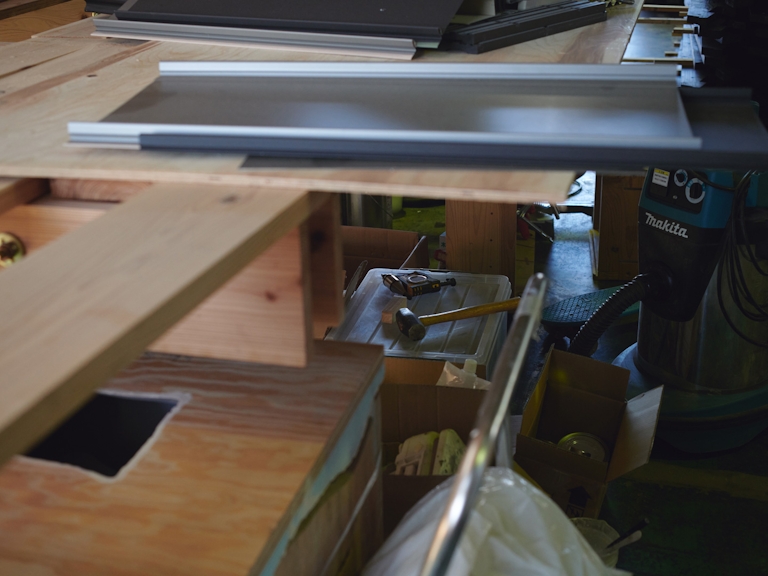
「自分のつくりたいものをつくる」のではなく、「誰かのためにつくることを支援する」ことが大切になる──このメタデザイナーに重要な観点は、NESTINGを運営するなかでも感じたという。
秋吉「余暇時間にセルフビルドで家をつくれるNESTINGは、つくった家に施主としてずっと住むだけでなく、それ自体を趣味やサブワークにすることも可能だと思うんです。セルフビルドで家を建てるコストが下がれば、家を建てて場所を転々としながら暮らすこともできる。
すなわち、家という“巣”をつくって育てたら、誰かにあげて次の場所に飛び立っていく……そんな使い方、『つくりながら暮らす』というライフスタイルも、僕たちのサービスを使えば実現できるかもしれない。そういう面白さを見出しています」
EMARFを使えるメタデザイナーが、地域で暮らしのなかで家をつくる。それができれば、ワーケーションのようにリモートワークで働くだけでなく、足を運んだ町や地域に「介入」できるかもしれない。こうした思考実験の延長にあるのが、香川県・小豆島でのプロジェクトだ。

小豆島 The GATE LOUNGE(撮影:太田拓実)
2023年7月にオープンした複合施設「小豆島 The GATE LOUNGE」では、地元企業とともに小豆島の島内にある木材を使用して、デジタル・ファブリケーションによって加工。施主自ら建築資材を調達して地産地消の建築を実現したこの施設は、「木造建築は島の外から木材を持ち込んでつくる」という従来の小豆島の常識を塗り替えて、「島内にあるものでつくる」という循環を生み出した。
秋吉「森も林業も島の中に存在しているはずなのに、いつしか島に木があることすら忘れてしまっている……島外から木材を輸入して産業や流通を外部化していく過程で、自分の個性を忘れてしまう。そこで僕たちの使命は、『あなたたちの島にも木はありますし、こういう風に使えばいいんじゃないですか』と問いかけることなんじゃないかと思うんです。
それは人間も同じで、現代の人々は自分が拠って立つ、自分らしさを見失っている。だからこそ、不安になったり、自己肯定感が低くなったりする人が増えているのではないかという気がします。『そもそも自分たちとは何だったのか』を見出して、暮らし方として家や家具などの形にしていく。そこで初めて個性や自分らしさが宿って、自分の生き方が育まれていくのではないかと思います」

「生態系」としての事業
ShopbotやEMARF、VUILD Place Lab、VUILD ARCHITECTS、そしてNESTING……「つくること」の民主化を目指して試行錯誤を繰り返してきたVUILD。
だが、ともすればスタートアップとしてこの事業形態は非合理的にも見える。複数事業が分散して存在し、かつ建築設計・施工など職人が手を動かして「一人工」といった単位で作業する受託業が含まれる事業形態は、短期的なスケールと上場を目指すスタートアップには不向きだからだ。
あえてそうした事業形態を採用している理由は、「自分たちがやれることの範囲で、着実にビジョンに向けて会社や事業を育てることを大切にしているから」だと秋吉は語る。
秋吉「僕たちの事業は、いわば“生態系”です。従来のスタートアップは1社1プロダクトが主流で、確実な市場の着実なニーズに向け全力投球して、手堅く上場を目指してゲームに勝っていく思考が一般的でした。
しかし、僕たちは事業やサービスの種を“同時並行”かつ“段階的”に発射している。例えば、受託事業で生まれた売上を、次は新事業のNESTINGに投資していく。長期的なビジョンの実現を第一に考えて、いま自分たちがやれることを積み上げ、少しずつ事業を収益化して育てています」

新たな施工の仕組みと、実際の事例づくりを平行して段階的に進めることで、VUILDは年輪のように事業を広げていく。
EMARFという新たな木材加工の仕組みをつくり、実際に手を動かして〈まれびとの家〉のようなユースケースをつくる。その知見を活かして、NESTINGというプラットフォームを新たに開発し、今度は自ら全国各地での家づくりの事例をつくっていく……こうした段階的な普及活動によって、使いこなすのが一般の人々には少し難しい技術でも、VUILD自身がその仕組みをよく理解しながら届けられる。
また、「自律分散」な世界のあり方を志向するVUILDにとって必要なのは、日本全国で一緒にムーブメントを起こす「同志」の存在だ。現状、EMARFユーザーには関東圏在住のインターネットやSNSに明るいタイプの人が多い。だが、すでにVUILDは全国各地にShopbotを長年かけて導入し、木材加工の環境整備を進めてきた。これからは同時多発的に「つくること」の民主化が起こる世界をつくるために、日本全国にその環境を使いこなす共同事業者を100社、1万人ほどに増やしていきたいと秋吉は語る。
そうした背景を踏まえて、2023年10月にVUILDはリブランディングを実施。創業から10年後の2027年に向けたミッション「つくる伴走者をつくる」を策定した。そして、VUILDという会社を「一本の樹のようなものである」とたとえながら、事業やメンバー、関係するステークホルダーが増加して多様化するなかで、VUILDが何を目指し、いかなる航路でそこにたどり着き、何を大事にしていきたいのかを改めて言語化したという。
秋吉「VUILDのビジネスは、哲学がベースにあり、ワクワクしたり、面白いと思ったり、心がときめいたり、魂が揺さぶられたりして、その上で『一緒にやりましょう』と行動してくれる人と一緒にやることが多いんです。理性的で合理的な判断ではなく、もう少し感覚的で情緒的で、感性的なものが響き合って初めてうまくいくことが多い。一緒にそういう未来を切り拓くために、いつもビジョンを起点に共謀者を探しています」

「つくること」の民主化は、手を動かしつづけることで拓かれる
VUILDが大きく舵を切り、ビジョンを見直していたタイミングにも、「つくること」の民主化を取り巻く状況は変わりつづけている。とりわけ近年の生成AIの発展はその大きな潮流の一つだと言えるだろう。
こうしたバズワード化の流れは、かつてWeb2.0やノーコードなど、何度も繰り返されてきた。泡のように盛り上がっては消えていく技術的なトレンドの波について、デジタル・ファブリケーションと「つくること」の民主化に一貫して取り組んできた秋吉は、どのように考えているのだろうか。
秋吉「誤解を恐れずに言えば、愚直に手を動かしてやり続けられる人が少ないと思います。以前はブームに乗って『次はデジタル・ファブリケーションだ』と口先で言っていた人が、次は『Web3だ』『生成AIだ』と鞍替えしていく姿を何度も見てきました。走ってもいないのにスタート地点でゴールについて語る人に投資が集まる構造も問題だと思います。
僕がひとつの技術領域を5年以上手がけてみてわかったのは、まずは自分たちがやり切らなければ、次にジャンプすべき課題が見えてこないことです。『机上の空論』かどうかは、やってみて初めてわかる。そこから何度もハードルを越えて、初めて本当の課題がわかり、徐々に理想に近づいていく。時間をかけて取り組み、愚直に技術や信用を積み上げていかなければ、未来に近づかないのだと思います」

技術を目的化しない。ウェブサイトを「Web1.0」とは呼ばないように、技術は後景化して初めて普及する。だからこそ、技術にばかり着目して語るだけでは先がない。あくまで身の回りにある生活や文化に接合されて、初めてその技術は花開く。
そうして技術が世界を変えていくあり方を模索しつづけるために、自分たちがやれることの範囲から着実に、「つくる伴走者」であるメタデザイナーを増やしながら、事業やステークホルダーとの関係性をじっくり育んで“生態系”を生み出していく。そして、その先に最終的に目指していることは、建築家、つくる人の復権である──「自分は建築家(アーキテクト)としてそこに取り組んでいる」と秋吉は締めくくった。
秋吉「歴史を遡ればルネッサンス以前の建築家は、決して表層のコンセプトを打ち上げて、綺麗なパースやビジュアルをつくって終わりの職業ではありませんでした。世の中に見えていないものを形として現実化する。そのために施工段取りをしたり、道具をつくったり、職人を育てたり、制度も作ったり、あらゆることをする仕事だったわけです。
しかし、身体性を伴った実行力に根ざしていたはずの建築家の職能は、職能分離によって失われてしまった。だから、いま建築家の職能はイメージを生成し続ける仕事に矮小化されている。それを覆していかなければ、世の中における建築家の社会的地位や影響力は変わっていきません。
『もしも昔の建築家が現代に生きていたら?』──僕はいつもそう考えて行動しています。そしてきっと、いまの僕と同じことをしてるんじゃないかなって。そんなことを考えているんです」

 Cover Stories
Cover Stories